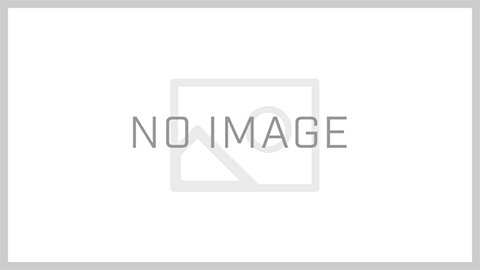「なんの味か説明できないけど、クセになる。」
そんな声が多く寄せられる炭酸飲料「ドクターペッパー」が、ついにアメリカでペプシを抜き、炭酸飲料シェア第2位の座に浮上しました。かつてはニッチでマニアックな飲み物とされていたドクターペッパーが、なぜいま若者の心をつかみ、人気を拡大しているのでしょうか?
この記事では、ドクターペッパーがアメリカで急成長した理由や、Z世代に刺さるマーケティング戦略、日本での入手方法などをわかりやすく解説します。ユニークな味わいと文化的ブームの裏にある、確かなデータと戦略に迫ります。
アメリカでドクターペッパーがペプシを抜き、シェア2位になった背景
アメリカ炭酸飲料市場の近年の動き
アメリカでは長年、炭酸飲料市場においてコカ・コーラとペプシがトップ2の座を維持してきました。この2社は「王者コカ・コーラ」と「対抗馬ペプシ」として互いにしのぎを削ってきましたが、2023年にこの勢力図がついに変わりました。なんと、長年3位だった「ドクターペッパー」がペプシを追い抜き、市場シェア第2位に浮上したのです。
この快挙はアメリカの業界専門誌「Beverage Digest」の発表に基づいており、販売量(ボリュームベース)においてドクターペッパーがペプシを超えたという信頼性の高いデータに裏付けられています。業界関係者やマーケティング担当者の間でも、この順位逆転は非常に大きなインパクトを持ち、食品業界紙や経済メディアでも広く報道されました。
この背景には、アメリカ人の炭酸飲料に対する意識の変化があります。かつては炭酸飲料=甘くてスッキリというイメージが定番でしたが、近年では「個性的な味を楽しみたい」「他人と違う選択をしたい」というZ世代のニーズが高まり、商品に求められる基準が変化してきています。その結果、従来の王道の味であるペプシが相対的に支持を落とし、代わりに“クセがあるけど癖になる”ドクターペッパーが人気を集めたのです。
さらに、ペプシは一定のブランドイメージを守り続ける傾向があり、大きな変化を好まないマーケティング戦略が裏目に出た面もあります。一方でドクターペッパーは、攻めのフレーバー展開やSNS連動のプロモーションなど、若年層にアピールする施策を積極的に展開しており、その差が結果としてシェア逆転に結びついたと考えられます。
Beverage Digest の最新データと順位変動
ドクターペッパーがペプシを抜いたという事実は、2023年に発表された「Beverage Digest」の炭酸飲料ランキングに基づいています。このデータは、アメリカ全土の小売店や飲食チェーンなどから集めた出荷情報や販売量をもとに算出されており、業界内では最も信頼性の高いデータソースとされています。
この調査結果によれば、1位は変わらずコカ・コーラですが、2位にドクターペッパーが浮上し、ペプシは3位へと後退しました。これは数十年ぶりに順位が変わる歴史的な出来事であり、ドクターペッパーにとってはブランド史上初の快挙です。
ドクターペッパーを展開する「ケリッグ・ドクターペッパー社」は、過去数年間にわたり、ゼロシュガー商品のラインアップ強化や、限定フレーバーの投入、若者向けのマーケティング戦略を積極的に展開してきました。その結果、単なる“ニッチ飲料”というイメージから脱却し、広い世代に受け入れられる「メインストリーム飲料」としての地位を確立することに成功しています。
特に注目すべきは、ペプシのシェアが急落したわけではなく、ドクターペッパーの売上が着実に上昇してきた点です。つまり、ペプシ離れというよりは、ドクターペッパーの新規ファンが急増した結果としての順位変動であり、これはブランドにとって非常に前向きな成長の証です。
このように、確かな統計データに裏打ちされたドクターペッパーの台頭は、今後の炭酸飲料市場においても重要な転換点となる出来事であり、他のブランドの戦略にも大きな影響を与えることが予想されます。
「ドクターペッパー」の味とフレーバーが人気を支える理由
23種類のフレーバーレシピとは何か
ドクターペッパーが他の炭酸飲料と一線を画す最大の特徴は、その「なんとも説明しにくい独特な味」にあります。飲んだ人が「これは何味なんだろう?」と首をかしげたくなるような、甘くてスパイシーでフルーティーな複雑な味わい。それこそが、ドクターペッパーの正体です。
この独特の味は、23種類のフレーバーがブレンドされたレシピに基づいています。これは製造元であるケリッグ・ドクターペッパー社が公式に発表している情報ですが、実際にどのフレーバーが使われているかは企業秘密とされています。しかし、長年にわたってファンの間でさまざまな分析が行われ、その中には次のようなフレーバーが含まれていると考えられています。
- チェリー
- アーモンド
- プラム
- シナモン
- バニラ
- リコリス(甘草)
- クローブ
- ジンジャー
- コーラ
- ブラックベリー
- ペッパー(黒胡椒のような風味)
このように、一つひとつでも個性の強い香料が絶妙なバランスで調合されており、それが飲んだときの「クセになる味」を生み出しています。いわゆる“薬っぽさ”があるという意見もありますが、それが逆に中毒性を高めていると感じる人も多く、「一度ハマったら抜け出せない」という声が少なくありません。
また、こうした味の複雑さは、コーラやスプライトなど他の炭酸飲料にはない個性であり、「自分だけが知っている特別な味」として、特にZ世代のような“違い”を重視する若者に刺さっています。SNSでも「何味か分からないけど美味しい」「飲めば飲むほどクセになる」といった投稿が多く見られ、味そのものが話題になるという特性を持っています。
さらにこの味は、ただの清涼飲料水ではなく「体験」として提供されているとも言えます。何度飲んでも同じ味に感じない、香りや後味が時によって変化するような感覚があり、毎回新鮮な驚きを楽しめるのです。この“味の奥深さ”が、ドクターペッパーを単なる飲み物ではなく、**「語りたくなる存在」**にしているのです。
このように、ドクターペッパーの味には明確な個性と戦略があり、それが長年にわたってファンを惹きつけ、現在の人気へとつながっています。
新しい限定・常設フレーバー例(ストロベリー&クリーム、クリーミーココナッツなど)
ドクターペッパーの人気を支えるもうひとつの大きな柱が、フレーバーの多様化戦略です。アメリカ市場では、定番のオリジナルフレーバーに加えて、期間限定や新規常設フレーバーの展開が積極的に行われており、それが新しいファン層の獲得に大きく貢献しています。
その中でも特に話題を呼んだのが、「ストロベリー&クリーム」フレーバーです。この商品は2023年にアメリカ全土でリリースされ、従来のドクターペッパーの風味にストロベリーの甘酸っぱさとクリームのまろやかさを加えた一品。まるでデザートのような味わいが特徴で、「飲むイチゴショートケーキ」と表現するファンもいるほどです。
また、「クリーミーココナッツ」や「チェリーバニラ」などの新しいフレーバーも発売され、どれもドクターペッパー特有の“奥深いベースの味”を維持しつつ、新しいアクセントを加えることに成功しています。これにより、ただ「変わり種を出している」だけではなく、ブランドとしての味の一貫性も保ち続けている点が評価されています。
これらの新商品は、特にZ世代の間で支持されており、TikTokやInstagramでは新作フレーバーの試飲動画やリアクション投稿が多数シェアされました。これがさらなる話題性を呼び、「試してみたい」という購買動機を自然に生み出す仕組みとなっています。
さらに、こうした新フレーバーの多くには「ゼロシュガー」バージョンも同時展開されており、カロリーや糖質を気にする層にもアプローチしています。特に健康志向が高まりつつある今の市場環境において、甘さを楽しみながらも罪悪感が少ない飲み物として、幅広い層に支持される要因となっています。
このように、定番の味に加えて、魅力的な変化球を繰り出し続ける姿勢が、ドクターペッパーのブランドを進化させ、人気を不動のものにしているのです。
Z世代とTikTokがドクターペッパー人気を爆発させた理由
若者の嗜好変化:ユニークさ・「違い」を求める傾向
Z世代を中心とする若者たちの消費傾向には、「自分らしさ」や「個性」を重視する特徴があります。飲み物に対しても、「みんなが飲んでいるから」よりも「自分の好きな味」「他の人と違うもの」に価値を見出す傾向が強まっています。そうした背景の中で、独特のフレーバーを持つドクターペッパーは、まさにZ世代の“求める飲み物像”にぴったりと一致したのです。
また、Z世代は「面白い」「クセがある」といった要素を好みます。ドクターペッパーの「薬のような味」や「クセになる甘さ」は、最初の印象こそ人を選びますが、一度気に入ればその個性が強く印象に残り、リピートにつながるという特徴があります。「なんとなく飲んでいる炭酸飲料」ではなく、「話題になる飲み物」「ツッコミどころのある味」として選ばれる存在となっているのです。
このような“ユニークで語れる体験”が、SNS時代の今、とくに価値を持っています。Z世代は飲んだ感想をそのままTikTokやInstagram、X(旧Twitter)に投稿し、リアクションを楽しむ文化があります。そのため、「味がよく分からないけど美味しい」「クセがあるのにまた飲みたくなる」といった声が拡散され、ドクターペッパーは自然発生的にバズを起こすようになりました。
ドクターペッパーは、こうした若者の心理や行動にうまく寄り添う形で、ブランドの魅力を浸透させています。特に「違いが武器になる」今の時代において、その個性はZ世代からの強い支持を得る大きな理由となっています。
TikTok上で流行するドリンクのカスタマイズ(例:ピクルスを加える、dirty sodaなど)
ドクターペッパーがZ世代に人気を広げる中で、特にTikTokが果たした役割は非常に大きいです。TikTokでは、ユーザーが独自のドリンクカスタマイズを紹介する「#DrinkTok」や「#SodaTok」などのハッシュタグが人気を集めており、その中でもドクターペッパーを使ったアレンジレシピが多数登場しています。
たとえば、アメリカで流行している「ダーティーソーダ(dirty soda)」はその代表例です。これはドクターペッパーやルートビアなどの炭酸飲料に、ココナッツクリームやバニラシロップ、さらにはライムやチェリーシロップなどを加えたカスタムドリンクで、「ちょっとジャンクでクセになる味」が人気を呼んでいます。
TikTokではこのダーティーソーダを自作する動画がバズり、数百万再生されることも珍しくありません。また、「ドクターペッパーにピクルスの汁を入れる」「ストロベリーシロップを追加する」など、一見奇抜とも思える組み合わせが次々と試され、視聴者の好奇心を刺激しています。こうした“遊び心あるアレンジ”が、さらにブランドの魅力を引き立てているのです。
このように、ドクターペッパーは飲み物としての役割を超え、「遊べる飲料」「SNSで話題にできる体験」としてZ世代の心を掴んでいます。ただ飲むだけでなく、カスタマイズしてシェアすることが当たり前になっている現代の若者文化の中で、ドクターペッパーはその中心に立つ存在となりつつあるのです。
マーケティングの観点から見ても、この現象は非常に価値があります。企業が広告を打たずとも、消費者自身がSNS上でプロモーションをしてくれるという、理想的な状態が生まれているからです。こうした“自走するバズ”を生み出せる商品は多くなく、ドクターペッパーが持つ味の個性とSNS時代の相性の良さが、人気拡大の大きな原動力となっています。
ソーシャルメディア広告・ブランド戦略の強化(限定フレーバーやストーリーテリング広告)
Z世代への影響力を高めるために、ドクターペッパーはSNSを中心としたマーケティングにも積極的に取り組んでいます。特にTikTokやInstagramでは、ドクターペッパーを使ったレシピ動画や短編ストーリー仕立ての広告が展開され、商品の世界観や楽しさを視覚的に伝える工夫がされています。
その一例が、「ドクターペッパーが悩みを吹き飛ばす存在」として描かれる短編広告です。退屈な毎日や仕事終わりの疲れに、一口飲めば気分が上がる――そんなポジティブなメッセージを込めた広告は、Z世代の「共感」に訴えかける内容になっています。
さらに、限定フレーバーの告知や販売もSNSを通じて発信され、フォロワー限定のキャンペーンや特典なども話題性を高めています。これにより、消費者は「今しか手に入らない」「みんなより先に試したい」という動機で行動し、購買につながるという流れが自然にできています。
また、Z世代は企業の“中の人”が発信する等身大のコンテンツにも共感しやすいため、ドクターペッパーの公式アカウントでは、堅苦しさのないユーモアや軽快なトーンでの投稿が多く見られます。これにより、ブランドとの距離感が近くなり、ファンとの信頼関係が築かれていきます。
このように、味の魅力に加えて**“デジタル空間でのふるまい”**も洗練されているドクターペッパーは、単なる飲料ブランドを超えて「カルチャーの一部」としてZ世代に受け入れられる存在になりつつあります。従来のマスメディア中心の広告ではなく、リアルタイムで反応が返ってくるSNSでの発信が、今後ますますブランド価値を高めていくでしょう。
“ドクターペッパー” 日本での入手方法とトレンドの可能性
日本で販売されているドクターペッパーの種類と輸入製品の状況(公式/非公式)
日本においても、ドクターペッパーは一部のファンから根強い人気を集めていますが、アメリカのようにスーパーの棚に常に並んでいるわけではありません。実際、日本での取り扱いは限定的であり、地域や流通チャネルによって入手難易度が大きく異なります。
まず、日本コカ・コーラ社が販売しているドクターペッパーが存在します。これは主に東京都や関東圏の一部自動販売機、ディスカウントストア、コンビニなどで見かけることができますが、全国展開はされていません。缶タイプやペットボトルが中心で、比較的スタンダードなオリジナルフレーバーのみが流通しています。
一方で、アメリカからの輸入製品として、バリエーション豊かなフレーバー(チェリーバニラ、ストロベリー&クリーム、ゼロシュガーなど)が販売されています。これらはコストコや成城石井、輸入食品専門店、またはAmazon・楽天などのECサイトを通じて手に入れることが可能です。価格はやや高めですが、「本場の味を楽しみたい」という層にとっては人気が高く、リピート購入する人も少なくありません。
また、並行輸入品にはパッケージデザインの違いもあり、コレクター的な楽しみ方をするファンも存在します。英語表記のラベルやアメリカの雰囲気がそのまま伝わる商品は、単なる飲み物以上に、ライフスタイルやカルチャーの一部として受け入れられているのです。
ただし、これらの輸入品は在庫が不安定なことも多く、「あの味が飲みたいのに売り切れている」といった声も少なくありません。日本国内での安定供給には課題がありますが、裏を返せば「レア感」が購買意欲を刺激しているとも言えます。
このように、日本でのドクターペッパーの流通状況は限られているものの、熱心なファンと輸入製品の存在によって一定の市場が形成されており、今後の拡大余地も残されています。
オンラインショップや個人輸入で買えるルート/注意点
日本国内でドクターペッパーを確実に手に入れるための手段として、オンラインショップや個人輸入は非常に有効です。特にAmazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの大手ECモールでは、さまざまなフレーバーがラインアップされており、タイミングによっては限定フレーバーが登場することもあります。
また、輸入食品専門の通販サイト(たとえば「ジュピター」や「KALDI ONLINE」など)でも、アメリカからの並行輸入品が取り扱われている場合があります。こうしたサイトでは、一定数まとめ買いすることで割安になるケースもあり、ファンにとっては見逃せない選択肢です。
個人輸入を行う場合は、海外通販サイト(たとえばアメリカのWalmart.comやeBayなど)を利用する方法もありますが、英語での注文手続きや国際送料、関税などの知識が必要になります。また、食品の個人輸入には規制もあるため、大量購入や商用目的での輸入には注意が必要です。
購入時に注意すべき点としては、「賞味期限」や「保管状態」です。特に輸入品の場合、輸送期間が長くなるため、届いた時点で賞味期限が近いことがあります。また、炭酸飲料は温度変化に弱いため、夏場の輸送や長期保管には注意が必要です。
一方で、こうした“手間”そのものも、ファンにとっては一種の楽しみでもあります。自分で探し、手に入れるというプロセスが、「ただ飲むだけ」で終わらない、体験型の消費につながっているのです。
日本での入手難易度が高いからこそ、ドクターペッパーは「特別な飲み物」としての価値を保ち続けており、その希少性がブランドの魅力をより高めているとも言えるでしょう。
日本で「コーラ飽きた」消費者からの選択肢としてのポジション
日本において、炭酸飲料の定番といえばやはりコカ・コーラが思い浮かびます。しかし、健康志向の高まりや味のマンネリ化によって、「コーラにはちょっと飽きた」「もっと違う刺激がほしい」と考える消費者も増えてきています。そんな中で、ドクターペッパーは**“第2の選択肢”**としてのポジションを徐々に築きつつあります。
その最大の理由はやはり、味の個性です。コーラやサイダーとはまったく異なる味わいは、まさに“新しい体験”として消費者に受け入れられています。特に20〜30代の若い層を中心に、「たまには違う炭酸が飲みたい」「クセがあるけどクセになる」といった理由からドクターペッパーを選ぶケースが増えています。
また、映画やドラマの中で登場するシーンに影響されて、ドクターペッパーに興味を持つ人も少なくありません。アメリカンカルチャーの象徴的な存在として、日本の若者文化にもじわじわと浸透してきているのです。
さらに、最近では「推し活」や「コレ活」の一環として、輸入フレーバーを集めたり、SNSで写真を投稿したりする人も増えており、飲み物としてだけでなく**“カルチャーアイテム”**としての価値も高まっています。
このように、コーラが当たり前すぎる時代だからこそ、「ちょっと違うものを飲みたい」というニーズにぴったり合うのがドクターペッパー。日本でもじわじわとその存在感を増しており、今後さらに注目される可能性が高まっています。
炭酸飲料トレンドの流れとドクターペッパーのポジショニング
アメリカ・グローバルでの炭酸飲料市場の縮小・健康志向の影響
ここ数年、アメリカをはじめとする先進国では、炭酸飲料市場の縮小傾向が続いています。これは、砂糖の摂取量を減らしたいという健康志向の高まりが背景にあります。特に成人だけでなく、若年層や親世代も子どもに砂糖を含む飲料を与えることに慎重になっており、ジュースや炭酸飲料の消費が見直されてきているのです。
実際、アメリカでは2000年代初頭から炭酸飲料の1人当たり年間消費量が年々減少しており、その代わりに炭酸水(フレーバー付きの無糖スパークリングウォーター)や、ゼロカロリー飲料、プロテインドリンク、コンブチャなどの健康系飲料が人気を集めています。世界全体でも同様の傾向が見られ、炭酸飲料市場の競争はますます激しくなってきています。
そんな中、ドクターペッパーは「健康路線」へのシフトだけではなく、「個性」と「体験価値」で勝負を仕掛けて成功しています。たとえば、ゼロシュガーラインの充実により健康志向のニーズには応えつつ、フレーバーの豊富さやユニークな味わいによって、「甘さ控えめでも面白い飲み物」という印象を定着させています。
つまり、ドクターペッパーは単に“健康に良い飲み物”を目指すのではなく、“飲む体験が楽しい炭酸飲料”という新しい立ち位置を確立しようとしているのです。これは、単なる低糖質志向だけでは満足しない若年層や好奇心旺盛な層に対して、非常に効果的なアプローチとなっています。
このように、全体的な炭酸飲料市場が厳しい状況にある中で、ドクターペッパーは新しい軸で市場に食い込み、成長を遂げている稀有なブランドといえるでしょう。
“ダーティーソーダ”(dirty soda)など新しい飲み方のトレンドとの結び付き
アメリカでは今、「dirty soda(ダーティーソーダ)」という新しい飲み方が若者の間で人気を集めています。これは炭酸飲料にフレーバーシロップやクリーム、フルーツピューレなどを加えて自分好みにカスタマイズするスタイルで、特にユタ州を発祥とするこの飲み方は、SNSで一気に広まりました。
ドクターペッパーはこのトレンドと非常に相性が良く、多くのレシピでベースの炭酸として使用されています。理由は単純で、元々が複雑なフレーバーを持っているため、アレンジしても味がボケにくく、よりリッチな味わいに進化させやすいからです。たとえば「ドクターペッパー+バニラシロップ+ココナッツクリーム」の組み合わせは、まるでクリームソーダのような贅沢な味わいとなり、大人から子どもまで楽しめると評判です。
また、こうした“遊び心”のある飲み方は、Z世代の価値観と非常に親和性が高く、自分だけのレシピをTikTokでシェアするなど、飲み物そのものを「創造的な体験」として楽しむ文化へとつながっています。ダーティーソーダのトレンドは、単なる一過性のブームではなく、炭酸飲料の新しい可能性を切り開くムーブメントとなっているのです。
ドクターペッパーは、この流れに自然に入り込み、時代の空気をうまく捉えてブランドの魅力を拡張しています。飲み方に幅があるということは、すなわち消費機会が広がるということであり、今後さらなる成長につながる大きな要素となるでしょう。
ドクターペッパーがコーラ/一般的な炭酸飲料との差別化をどのように進めているか
炭酸飲料市場では、多くの製品が「コーラ風味」「果実系」「クリームソーダ系」といった分類に収まる中、ドクターペッパーはそのどれにも明確に当てはまらない独特なポジションを確立しています。この“カテゴライズできない味”こそが、他の炭酸飲料との差別化の最大のポイントです。
さらに、ブランドの打ち出し方にも一貫した個性があります。広告では「23のフレーバー」「クセになる味」「誰にも真似できない個性」といったキーワードを前面に出し、他のどの飲み物とも違う“特別感”を強調しています。これにより、消費者の中に「ドクターペッパー=唯一無二」という印象が定着し、ロイヤリティの高いファンを生み出しているのです。
また、ドクターペッパーは“挑戦する飲み物”としての魅力も持っています。初めて飲む人にとっては衝撃的かもしれませんが、それが逆に「冒険心をくすぐる飲み物」としての価値を生み出しています。これは、ありきたりな選択肢に飽きた人や、新しい味を求める人にとって、強いアピールポイントとなります。
一方で、味だけでなく、商品ラインアップでも差別化が図られています。ゼロシュガーシリーズ、限定フレーバー、パッケージデザインの多様性など、細部にわたる戦略によって、「一度だけではなく何度でも試したくなる」ブランド体験が構築されています。
このように、ドクターペッパーは味、飲み方、ブランディングのすべてにおいて他とは違う道を選ぶことで、炭酸飲料市場における独自のポジションを確保しています。今後も変化する消費者ニーズに応じて進化し続けることが期待されるブランドです。
まとめ
ドクターペッパーがアメリカでペプシを抜いて炭酸飲料シェア第2位になったというニュースは、一時的なブームではなく、明確な戦略と時代の流れが生んだ必然的な結果だといえます。Z世代を中心に、「みんなと違うものを選びたい」「ちょっとクセがある方が面白い」といった嗜好の変化が広がりつつある中で、ドクターペッパーはその個性的な味と多彩なフレーバー展開で、しっかりと支持を集めてきました。
また、TikTokやInstagramなどのSNSを活用したマーケティングや、ユーザー自身がカスタマイズを楽しむ「ダーティーソーダ」などの飲み方の提案によって、ドリンクそのものを“体験”として楽しむスタイルを確立しています。こうした取り組みがブランドの成長に大きく寄与しており、特にZ世代との親和性の高さは、今後のさらなる躍進を予感させます。
日本でも、輸入製品の人気や「コーラに飽きた」層の受け皿としての存在感が高まりつつあります。手に入りにくいからこそ、特別感を感じる人も多く、その“レア感”がブランド価値をさらに高めています。
炭酸飲料市場全体が健康志向や代替飲料の台頭によって変化している中で、ドクターペッパーは「味の個性」と「カルチャー性」という独自の軸で差別化を進めています。その結果が、ペプシを超えるという歴史的快挙につながったのです。
これからも、ただの飲み物にとどまらず、“話題になる存在”として、ドクターペッパーがどのように進化を続けていくのか注目が集まります。