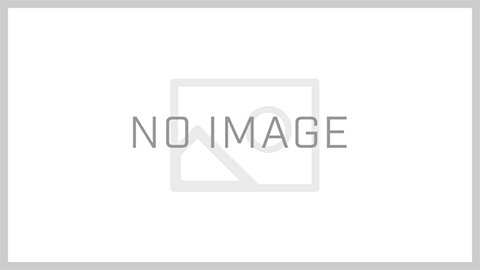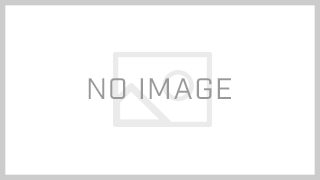TBSの人気番組『クレイジージャーニー』で紹介された“アドベンチャーレース”に衝撃を受けた人は多いはずです。
ジャングルを突き進み、寝ずに山を越え、川を渡り、数日間ゴールを目指す…。
そんな常軌を逸したスポーツに、日本人チーム「イーストウインド」が挑む姿は、まさに“狂気と感動のドキュメンタリー”でした。
でも、見ているうちにこう思いませんでしたか?
「このアドベンチャーレースって、実際どんな競技なの?」
「日本でもできるの?初心者でも参加できるの?」
「装備や費用、賞金ってどうなってるの?」
その疑問が頭から離れなくて、自分で徹底的に調べてまとめました。
この記事では、アドベンチャーレースの基本から、国内大会情報、初心者の始め方、実際のコスト、そして夢の“世界レース”の裏側まで、わかりやすく解説しています。
「観る」だけで終わらせたくない人へ。
あの感動と興奮を、次は“自分の体”で味わってみませんか?
日本でも体験できる!アドベンチャーレースとは?
アドベンチャーレースの定義と特徴
アドベンチャーレースとは、山や川、森など自然の中で複数の競技を連続して行う耐久型のチームレースです。一般的には「トレッキング(登山)」「マウンテンバイク」「パドリング(カヤックなど)」の3種目を中心に構成され、競技によっては「ロープワーク」や「オリエンテーリング(地図とコンパスを使ったナビゲーション)」も含まれます。競技時間は数時間の短距離レースから、10日以上にわたる超長距離のレースまでさまざまです。
アドベンチャーレースは、他のスポーツと違って「チェックポイント(CP)」を自分たちで地図から探し出し、決められた順序で通過していく必要があります。しかも、それを行うのはGPSやスマートフォンの地図ではなく、紙の地図とコンパスが基本。つまり、単に体力があるだけでは勝てない、頭脳と戦略性が問われるスポーツなのです。
また、アドベンチャーレースは基本的に「チーム戦」で行われます。国際ルールでは、男女混合の4人チームがスタンダード。1人でもリタイアすればチームは失格になるため、仲間との信頼関係やコミュニケーション能力も極めて重要です。疲労やトラブルが続くなかで、いかにチームとして乗り越えていくかが大きな見どころのひとつとなっています。
このスポーツが特徴的なのは、「レース中に眠らない」こともあります。世界レベルの大会では、ほとんど睡眠を取らずに100時間以上走り続けるチームもあるほど。まさに人間の限界を試す過酷な冒険レースです。
このように、アドベンチャーレースは肉体的にも精神的にもタフさが求められる「究極のチームスポーツ」といえるでしょう。ですが、その過酷さの先にある達成感や感動は、他のスポーツでは味わえないものがあります。自然の中で、自分と仲間の限界に挑戦する——それこそが、アドベンチャーレースの最大の魅力です。
次は「世界の代表的なレースと日本の違い」の執筆に進みます。
日本でも体験できる!アドベンチャーレースとは?
世界の代表的なレースと日本の違い
アドベンチャーレースは世界各地で開催されており、その中でも特に注目されているのが「Adventure Racing World Series(ARWS)」です。このシリーズは、世界選手権を含むグローバルな大会群で構成されており、選ばれたチームたちは約600km以上の過酷なコースを、6日〜10日間かけて走破します。代表的な大会には、ニュージーランドの「GODZONE」や、パタゴニアで行われる「Expedition Race」、アメリカで開催された「Eco-Challenge(エコチャレンジ)」などがあります。
これらの世界的な大会は、非常にスケールが大きく、山岳地帯、ジャングル、海、川といった多様な自然環境を舞台にして行われます。参加チームはGPS機器を封印された状態で、地図とコンパスだけを使いながら、極限状態で進んでいきます。賞金が出るレースもあり、AR World Championshipでは数万ドル規模の賞金が設定されていることもあります。
一方で、日本国内で開催されているアドベンチャーレースは、距離や日数の点で比較的コンパクトなものが多く、2日間以内、100km前後のレースが中心です。例えば、北海道で開催される「ニセコアドベンチャーレース」や、関西エリアで行われる「アドベンチャーゲーム」などがその代表例です。中には数時間で終わる「エクストリームシリーズ」のような短距離レースもあり、初心者でも参加しやすい環境が整っています。
また、日本では参加チームの数も世界に比べてまだ少なく、スポンサーやメディアの注目度も限定的です。そのため、賞金が設定されているレースは非常に少なく、参加者の多くは純粋に「冒険」や「達成感」を求めて挑戦しているのが現状です。
とはいえ、日本の大会にも独自の魅力があります。例えば、四季折々の美しい自然、里山や温泉地など地域の文化と連動したレース設計などは、海外にはない特色です。また、安全面の配慮も行き届いており、初心者でも安心して参加できるような運営がされている点も評価されています。
このように、アドベンチャーレースは世界と日本で規模や目的に違いはありますが、「自然の中で自分の限界に挑む」という本質はどちらも共通しています。これからアドベンチャーレースに興味を持った方は、まずは日本国内の大会からスタートし、将来的に世界へ挑戦することも夢ではありません。
競技内容:トレッキング・MTB・カヤックの基本
アドベンチャーレースでは、複数のアウトドア競技が組み合わされており、その中でも特に基本となるのが「トレッキング(登山)」「マウンテンバイク(MTB)」「カヤック(パドリング)」の3つです。これらは自然環境の中で長時間にわたって行われるため、体力だけでなく技術や経験、安全意識も求められます。
まずは「トレッキング」ですが、これはいわゆる登山やトレイルランに近いイメージです。舗装されていない山道や森の中を、自分たちの足で進んでいきます。大会によっては高低差の激しい山岳地帯を夜間に移動することもあり、地図読みや体力の消耗管理が非常に重要になります。疲れていても道を見失えば大幅なタイムロスになるため、正確なナビゲーション能力がカギを握ります。
次に「マウンテンバイク(MTB)」は、未舗装の林道やシングルトラック(細い山道)を走る種目です。長距離を走行するだけでなく、急坂や岩場、滑りやすい下り坂など、さまざまな難所を越えていかなければなりません。自転車の操作スキルや安全に走るための装備管理、さらにはパンクなどのトラブル時に自分で修理する力も必要です。特に長距離のレースでは、夜間走行を行うこともあり、ヘッドランプやテールライトなどの装備も不可欠です。
そして「カヤック(パドリング)」は、川や湖、海といった水上での移動を行います。基本的には2人乗りのシットオンタイプのカヤックが使用されることが多く、静水・流水問わず自力で漕ぎ進める必要があります。水上では天候や風の影響を強く受けるため、体力以上に冷静な判断とチームワークが求められます。また、転覆に備えてPFD(ライフジャケット)の着用が義務づけられており、安全意識が特に重視されるパートです。
これら3つの競技は、自然の地形をそのまま活用したステージで行われるため、予想外のハプニングもつきものです。大雨でぬかるんだ登山道、パンクだらけの自転車コース、風で流されるカヤックルートなど、何が起こるかわからない中で進むのがアドベンチャーレースの醍醐味でもあります。
初心者がこれらに挑戦する際には、個別にトレーニングするのも良いですが、まずは短時間のレースや体験会などに参加して、実際にやってみることが一番の近道です。それぞれの種目で必要な装備や注意点を体感しながら、少しずつ経験を積んでいくことで、アドベンチャーレースの世界がぐっと身近になります。
なぜこんなに過酷なのか?魅力と中毒性
アドベンチャーレースは、ただのアウトドアスポーツとはまったく違います。その最大の特徴は、極限状態で長時間にわたって体と心を酷使し続けるという、常識では考えられないほどの「過酷さ」です。にもかかわらず、多くの人が一度参加したらハマってしまうという“中毒性”を持っています。なぜこれほどまでに過酷でありながら、人を惹きつけるのでしょうか?
まず、アドベンチャーレースが過酷といわれる理由のひとつは「睡眠時間の少なさ」です。世界大会クラスのレースでは、5日間で合計睡眠時間が5時間以下というチームも珍しくありません。移動距離も500km以上に及ぶ場合があり、山を越え、川を渡り、夜通し進み続けることが求められます。体力的な限界はもちろん、精神的にも追い込まれる状況が続きます。
また、ナビゲーションも難しさの要因です。GPSを使えず、地図とコンパスのみで進むため、ミスをすれば数時間のロスになることも。体が疲れているときに、正確な判断力を維持するのはとても難しく、集中力とチームワークが試される瞬間が何度も訪れます。
では、なぜそこまでして挑戦したくなるのでしょうか?
その答えは、アドベンチャーレースならではの「非日常体験」にあります。山奥の絶景、夜明けの湖、誰もいない渓谷をチームで乗り越える体験は、言葉では表せないほどの感動を与えてくれます。自然と一体になる感覚、自分の限界を突破したときの達成感、仲間と共有する絆——これらは、日常では決して味わえない特別なものです。
さらに、アドベンチャーレースは「競争」であると同時に「冒険」でもあります。順位やタイムを争うだけでなく、自分自身と向き合い、自然と向き合う時間を持てるのです。この“生きている実感”が、多くの人を魅了し、「もう二度とやらない」と言いつつも、また次のレースに申し込んでしまう……という中毒性に繋がっているのでしょう。
もちろん、誰にでも簡単にできるスポーツではありません。しかし、だからこそ価値があり、自分の殻を破りたい、挑戦したいという気持ちを持つ人にとっては、これ以上ない魅力的なフィールドなのです。
観るだけでも面白い「クレイジージャーニー」で話題の理由
アドベンチャーレースが一般層にも知られるようになった大きなきっかけのひとつが、TBSの人気ドキュメンタリーバラエティ番組『クレイジージャーニー』です。この番組は、常人では考えられないような挑戦や探検を続ける人物に密着するという内容で、アドベンチャーレース日本代表チーム「イーストウインド」が取り上げられたことで、瞬く間に注目を集めました。
番組では、イーストウインドのリーダー・田中正人さんを中心に、彼らが世界中のレースでどれほど過酷な挑戦をしているのかが、リアルな映像とともに紹介されました。熱帯雨林の中を何日も眠らずに進み続ける姿、泥にまみれながらのカヤック、仲間とぶつかりながらも助け合ってゴールを目指すチームワーク……そのどれもが、まさに“クレイジー”の名にふさわしい内容でした。
この放送を見て、アドベンチャーレースを「人間ドラマ」としてとらえる視聴者も増えました。単なるスポーツではなく、極限状況の中での決断、失敗、成長、仲間との信頼、そして感動のゴール——まるで映画のようなリアルなストーリーが、視聴者の心を強く打ったのです。
特に印象的だったのは、競技中にメンバーの体調が急変したり、道に迷って何時間もさまよったりする場面。それでも諦めずに立ち上がる姿に、多くの視聴者が勇気や感動をもらったとSNSでも話題になりました。アドベンチャーレースの世界を知らなかった人たちが、「こんな世界があるんだ」と驚き、興味を持つきっかけとなったのは間違いありません。
また、クレイジージャーニーでは、ただ過酷なだけでなく、アドベンチャーレースの持つ哲学や自然との向き合い方、人とのつながりの深さにも触れていた点が高く評価されています。出演した田中正人さんが語った「ゴールすることよりも、どうゴールに向かうかが大事」という言葉には、多くの人が共感を覚えたことでしょう。
このように、アドベンチャーレースは観るだけでも十分に面白く、感動や気づきを与えてくれるコンテンツです。最近では、YouTubeなどでも大会のダイジェストや選手の記録映像が公開されており、まずは“観る”ことからこの世界に触れてみるのもおすすめです。
日本のアドベンチャーレース事情
国内で開催されている代表的なレース
日本国内では、いくつかのアドベンチャーレースが定期的に開催されています。代表的な大会として知られているのが「NISEKO EXPEDITION(ニセコ・エクスペディション)」です。この大会は北海道・ニセコエリアを舞台に開催され、マウンテンバイク、トレッキング、パドリング、ナビゲーションなど本格的な要素が詰まったステージが用意されています。地元の美しい自然と厳しい地形が選手たちを待ち受け、数日間かけてゴールを目指す中・上級者向けの大会です。
もう一つ、全国的に展開されているのが「エクストリームシリーズ」。このシリーズは初心者向けにも対応しており、日帰りや1泊2日のコンパクトな構成が魅力です。東京、関西、九州など各地で開催されており、参加者は年齢や経験を問わず気軽にチャレンジできます。多くの大会でレンタル装備が用意されているのもポイントです。
また、ファミリーや地域参加型のイベントとして注目されているのが「東伊豆アドベンチャーラリー」や「里山アドベンチャー」。これらは小学生や親子でも参加できるルールとなっており、アドベンチャーレースの入門編として非常に人気があります。参加者が自然や地域文化に触れながら楽しめる工夫が随所に見られます。
このように、日本国内ではレベルに応じた多様な大会が開催されており、自分の体力や経験に合わせて選べるのが魅力です。公式サイトやSNSを通じて情報が公開されているため、初めての人でも参加しやすい環境が整っています。
地域ごとのレースの特徴(北海道・長野・九州など)
アドベンチャーレースは、地域の地形や文化と密接に関わって開催されるため、開催地によって特徴が大きく異なります。たとえば、北海道では「NISEKO EXPEDITION」や「洞爺湖周辺」で行われるレースがあり、広大な山岳地帯と美しい湖が魅力です。自然環境が豊かで、長距離のステージや夜間移動が含まれる本格派の大会が多いのが特徴です。
長野県では、アルプスの山岳地形を活かしたトレッキングやマウンテンバイクが中心の大会が行われることが多く、標高の高低差が大きいため体力が問われます。夏でも涼しい気候と豊かな森林環境が、タフな競技をさらに過酷にします。
九州エリアでは、阿蘇や霧島など火山地帯を舞台にしたレースが開催されることがあります。火山性地形を活用したダイナミックなコース設定が特徴で、温泉地や地元食材とのコラボなど、観光要素と結びついた大会が多く見られます。
地域によっては、地元の観光協会や自治体と連携して開催されており、レース後に地域の魅力を体験できるアクティビティがセットになっているケースもあります。これにより、参加者は「スポーツ」と「旅」の両方を楽しめるのが大きな魅力です。
このように、日本各地の自然や文化を活かしたアドベンチャーレースは、それぞれに個性があり、何度出ても飽きることがありません。毎年違う地域の大会に参加することで、新しい発見や出会いが生まれるのも、このスポーツの楽しさのひとつです。
「イーストウインド」だけじゃない!注目の日本チーム
日本のアドベンチャーレースチームといえば、真っ先に名前が挙がるのが「イーストウインド(EAST WIND)」です。田中正人さん率いるこのチームは、世界の名だたるレースに出場し、過酷な環境下で数々の好成績を収めてきたトップチーム。テレビ番組『クレイジージャーニー』にもたびたび出演し、一般層にもその存在が知られるようになりました。
しかし、日本にはイーストウインド以外にも、世界で活躍しているチームがいくつか存在しています。たとえば、「KATANA Adventure」や「Team Chomolungma」「EZO MOMONGA 123」などは、アジア圏のARWS(アドベンチャーレースワールドシリーズ)予選大会などに継続的に参加しており、着実に実力を伸ばしている注目チームです。
これらのチームは、必ずしもプロではなく、それぞれ本業を持ちながら、週末や休日を使ってトレーニングとレース活動を行っています。つまり、一般人でも努力と情熱次第で国際大会に挑戦できることを証明している存在でもあります。
また、若手の選手たちによる新しいチームの結成も活発で、SNSを活用した情報発信やクラウドファンディングで活動資金を募るなど、現代的なスタイルでレースに挑む姿も見られます。
日本発のチームが、世界のフィールドでどのように戦い、成長していくのか——その挑戦は、日本のアドベンチャーレース界全体の希望と言えるでしょう。
日本でアドベンチャーレースが盛り上がらない理由とは?
世界では人気が高まっているアドベンチャーレースですが、日本ではまだまだマイナースポーツの域を出ていないのが現実です。その背景にはいくつかの要因があります。
まず1つは、「知名度の低さ」です。日本ではテレビ放送や大手メディアで取り上げられる機会が少なく、そもそもアドベンチャーレースの存在を知らない人が多いのが現状です。また、観戦型のスポーツではないため、視聴者として楽しむ機会が少ないというのも理由のひとつです。
次に、参加のハードルが高いことも挙げられます。競技にはある程度の体力、技術、装備が必要で、初心者がいきなり本格的な大会に出るのは難しいと感じる人が多いです。さらに、複数人のチームで行動する必要があるため、「仲間集め」がネックになるケースもあります。
また、日本では山や川など自然環境の多くが私有地や保護区域に指定されており、大規模なコースを設定しづらいという事情もあります。大会開催のための許可取得や安全対策に多大な労力が必要なことも、普及の壁になっています。
このような課題を解決するには、初心者向けイベントの拡充や、SNSやYouTubeを活用した情報発信、自治体や観光地との連携強化などが鍵となるでしょう。
海外との違いから見える日本の課題と希望
アドベンチャーレースが盛んな海外と比べると、日本の課題は明確です。海外では国際大会がスポーツツーリズムとして認知され、地元の行政や企業が積極的にスポンサーとなり、観光振興や地域活性化の一環として大会を支えています。一方で、日本ではそのような動きがまだ限定的で、運営はほぼボランティアや有志によって支えられているのが現実です。
また、海外ではアウトドアスポーツが教育の一環として取り入れられている国も多く、幼少期から自然に親しむ文化が根づいています。これに対し、日本では「自然=危険」と考える傾向が強く、子どもたちが外で遊ぶ機会が減っているのも一因です。
とはいえ、日本でも希望はあります。近年では地方自治体が地域活性化のためにアドベンチャーレースを取り入れる事例が増え始めており、観光資源とスポーツを結びつけた新しい取り組みとして注目されています。若い世代によるチームやイベント運営も増えており、SNSを通じた発信によって徐々にファン層を拡大しています。
今後、日本独自の文化や自然を活かした「日本らしいアドベンチャーレース」が確立されていけば、世界に誇れるアウトドアスポーツとして定着していく可能性は十分にあるでしょう。
初心者でも挑戦できる!アドベンチャーレースの始め方
まずはミニレースから!初心者向け大会紹介
アドベンチャーレースに興味はあるけれど、「自分には無理そう」「体力が心配」という初心者の方におすすめなのが、まずは短時間・短距離のミニレースに参加することです。日本では初心者向けの大会が各地で開催されており、誰でも気軽にチャレンジできる環境が整っています。
代表的な大会が「エクストリームシリーズ」です。このシリーズは、東京・関西・九州など全国で定期開催されており、日帰りまたは1泊2日で完結するのが特徴です。種目も簡略化されており、5〜10kmのトレッキングやサイクリング、軽めのパドリングなど、入門者に優しい構成になっています。競技中にスマホの使用が許可されている大会もあり、ナビゲーションに不安がある人でも安心です。
もうひとつの例が、「東伊豆アドベンチャーラリー」。こちらは小学生や親子でも参加できる内容で、レースというより“自然体験型の冒険イベント”に近い形式です。チェックポイントを探しながら自然の中を移動することで、アドベンチャーレースの雰囲気を味わいつつ、無理なく楽しむことができます。
初心者向け大会では、多くの参加者が「アドベンチャーレースは初めて」という人たちばかりです。そのため、競技前にしっかりしたブリーフィング(説明会)があり、運営側のサポートも手厚いのが魅力です。また、装備のレンタル制度を設けている大会も多く、道具を持っていない人でも気軽に参加できる点が好評です。
まずは「楽しむこと」が目的のライトな大会からスタートし、少しずつ距離や難易度を上げていくことで、無理なくアドベンチャーレースの世界に入っていけます。何よりも大切なのは、「完走しなければいけない」というプレッシャーを感じず、自分のペースで自然の中を仲間と一緒に進む体験を楽しむことです。
必要な装備とトレーニング方法
アドベンチャーレースに挑戦するためには、種目に応じた基本的な装備と、それを使いこなせる体力・スキルが必要です。初心者向けの短距離レースでも、しっかり準備しておくことで、安全かつ楽しくレースを楽しむことができます。
まずは、最低限必要な装備から見ていきましょう。
基本装備チェックリスト(初心者向け)
| 種別 | 具体例 |
|---|---|
| ウェア類 | 動きやすいアウトドアウェア、レインウェア、速乾性インナー |
| シューズ | トレイルラン用シューズまたは軽登山靴 |
| バックパック | 10〜20L程度、ハイドレーション対応が便利 |
| ナビ用品 | コンパス、地図(大会側で配布)、地図読み用ルーペなど |
| 照明 | ヘッドランプ(夜間走行に備えて)、予備電池 |
| 水分・補給 | ハイドレーション、行動食(ジェル・ナッツ等) |
| 安全用品 | ファーストエイドキット、ホイッスル、保険証のコピーなど |
| その他 | グローブ、サングラス、防寒着、耐水バッグなど |
大会によっては、パドルや自転車、PFD(ライフジャケット)などの装備が必携品となる場合もありますが、多くの初心者向け大会ではレンタルが用意されているため安心です。ただし、自分の体に合う装備を使った方が疲れにくく、トラブルも防げます。
次に、トレーニングについてです。アドベンチャーレースは長時間の運動が前提となるため、持久力が重要になります。いきなり山登りやバイクに挑戦するのではなく、以下のようなメニューで基礎体力をつけるのがおすすめです。
- 週2〜3回のジョギング(30分〜1時間)
- 休日に低山ハイク(5〜10km程度)
- 自転車通勤や週末サイクリング(距離よりも継続)
- 体幹トレーニング(プランク、スクワットなど)
- ロープワークや地図読みの練習(YouTubeや講習会を活用)
最初は筋力よりも「続ける力」を重視して、無理なく習慣化することがポイントです。競技に必要なスキルはレースに参加しながら自然と身についていきますし、仲間と一緒に練習することで楽しさも倍増します。
また、初心者向けのワークショップや体験イベントに参加するのも良い方法です。実際のフィールドで装備の使い方やルール、ナビゲーションを学べる機会はとても貴重です。何より、経験者のアドバイスを直接聞けることで、不安や疑問が一気に解消されます。
装備とトレーニングの準備が整えば、あとは一歩を踏み出すだけです。「完璧じゃないとダメ」と思わず、まずは自然の中を楽しむ気持ちで始めてみましょう。
チームの組み方と仲間探しのコツ
アドベンチャーレースのほとんどは「チーム制」で行われるため、仲間探しは非常に重要なステップです。特に公式ルールに基づくレースでは、3〜4人の男女混合チームが標準。初心者にとって「一緒に走ってくれる仲間がいない…」というのが最初の壁になりがちですが、実は探し方にはコツがあります。
まず、最も手軽なのがSNSでの募集・参加です。X(旧Twitter)、Instagram、Facebookのグループや「アドベンチャーレース仲間募集」などのコミュニティでは、メンバーを探している人が定期的に募集投稿をしています。過去の大会名やチーム名で検索すれば、経験者とつながることも可能です。
次に、大会公式サイトや団体の掲示板を活用する方法があります。例えば、「エクストリームシリーズ」や「東伊豆アドベンチャーラリー」などの大会では、公式にチームメンバー募集掲示板や問い合わせフォームが用意されていることがあります。主催者側がマッチングを手伝ってくれる場合もあり、初参加でも安心してエントリーできます。
また、体験イベントや講習会に参加して顔を広げるのも非常に有効です。アドベンチャーレース関連の団体が主催する「体験レース」や「ナビゲーション講習」では、同じレベルの初心者が集まるため、そこから自然にチームが生まれることが多いです。実際に顔を合わせて一緒に動くことで、信頼関係も築きやすくなります。
仲間を見つけるときに大切なのは、「体力のレベル」や「目標の温度感」をすり合わせることです。「完走を目指したい人」と「順位を狙いたい人」が混ざると、レース中に意見がぶつかることも。事前にお互いの目標や得意・不得意な競技を確認しておくことで、チームワークがスムーズになります。
なお、「どうしても仲間が見つからない…」という人向けに、最近ではソロ参加OKのレースや、運営がチームを編成してくれる制度を導入する大会も増えてきました。最初はそういった大会を利用し、現地での出会いからチームを組むという流れも十分にアリです。
アドベンチャーレースは、ただの体力勝負ではありません。むしろ、「信頼できる仲間」とのチームワークが一番のカギになります。思い出にも、学びにも、達成感にもなる。そんなかけがえのない仲間と出会うところから、あなたの冒険が始まります。
参加費用はどのくらい?実際のコストを紹介
アドベンチャーレースに興味を持ったときに、多くの人が気になるのが「お金の話」です。特に初心者の場合、「どれくらい費用がかかるの?」という疑問は非常に現実的。実際のところ、レースの規模や形式によって必要なコストは大きく変わってきますが、ここでは初心者が参加しやすい国内レースを中心に、費用の目安を紹介します。
まず、参加費は大会によって幅があります。たとえば、エクストリームシリーズのような日帰りの初心者向けレースであれば、1人あたり4,000〜8,000円程度が一般的。1泊2日で開催される場合でも、10,000〜15,000円以内に収まるケースが多いです。ファミリー向けや自治体主催のイベントであれば、さらに安価(数千円程度)で参加できることもあります。
次に、交通費と宿泊費。これは開催地や参加スタイルによって大きく変動しますが、都市圏から遠方の山間部で開催される場合、往復の交通費(新幹線・レンタカーなど)で1万円〜2万円程度、前泊が必要な場合は宿泊費が5,000円〜1万円程度かかると見ておくと良いでしょう。
また、装備費用も重要なポイントです。初めての参加で装備を一からそろえると、以下のような費用がかかります:
| 装備項目 | 費用目安(新品) |
|---|---|
| トレイルランシューズ | 約10,000〜15,000円 |
| バックパック(10L) | 約5,000〜10,000円 |
| コンパス・地図用品 | 約2,000〜5,000円 |
| ヘッドランプ | 約3,000〜8,000円 |
| ウェア類(レイン含む) | 約10,000〜20,000円 |
合計でざっくり3万円〜5万円前後かかる計算になりますが、初心者向け大会ではレンタル装備を用意している場合もあり、費用を抑えたい人は活用するのがおすすめです。
なお、これらはあくまで参考値であり、実際には既に持っているアウトドア用品を流用することでかなり節約できますし、仲間とシェアしたり中古品を活用するなど、工夫次第でコストダウンも可能です。
最初から全てを完璧にそろえる必要はなく、まずは「最低限の安全を確保できる装備」と「楽しむ心」を持って、無理のない範囲で始めることが、アドベンチャーレースを長く続けるコツです。
初出場で気をつけたい5つのポイント
初めてアドベンチャーレースに出場する際、知っておくと安心なポイントがいくつかあります。ここでは、初心者がつまずきがちな場面を避けるための「5つの心得」をご紹介します。
- 事前の下調べは入念に!
参加する大会の公式サイトや配布資料をしっかり読み込みましょう。ルール、装備リスト、コース概要などを把握しておくことで、当日になって慌てることがなくなります。 - チームでのコミュニケーションを大切に
アドベンチャーレースはチームスポーツです。「ついていけるかな?」という不安は誰もが持っていますが、無理せず自分の状態を共有することが何より大切。普段からLINEやミーティングで意思疎通を深めておくと、レース中の信頼にもつながります。 - 装備チェックを怠らない
前日には必ず装備を一式広げて確認しましょう。ヘッドランプの電池切れ、コンパスの紛失、水分の不足など、些細な忘れ物が大きなトラブルにつながります。チェックリストを使うと安心です。 - スピードより完走を意識しよう
初参加では順位を狙うよりも、まず「全員で完走すること」に焦点を置くのがおすすめです。無理なペース配分は体力の消耗を早めるだけでなく、ナビミスやケガにもつながります。 - 体調と気候の変化に敏感になろう
特に夏や山岳エリアの大会では、天候の急変や熱中症への対策が重要です。汗冷えや脱水を防ぐために、レイヤリングやこまめな水分補給を意識しましょう。日焼け止めや虫よけも忘れずに。
初出場は何かと不安が多いですが、どんなベテラン選手でも最初は初心者です。大切なのは「楽しむこと」と「無事に帰ること」。安全を最優先に、思い出に残る最高の冒険を体験してください。
世界大会の賞金と副賞の相場
アドベンチャーレースは「過酷な冒険」というイメージが強く、「報酬なんてあるの?」と思われがちですが、実は世界レベルの大会では賞金が設定されていることもあります。特に「Adventure Racing World Series(ARWS)」の世界選手権や、米国で開催された「Eco-Challenge」などは、高額な賞金を設けていることで知られています。
ARWSの世界選手権では、近年の賞金総額が**5万ドル(約750万円)**規模となっており、優勝チームには2万ドル以上が授与されることもあります。また、上位入賞チームに副賞(高額なアウトドア用品やスポンサー製品)や次回大会の招待権などが提供される場合もあります。こうした世界大会では、スポンサー企業が支援に入り、賞金を通じて選手の活動をサポートしているのです。
さらに、テレビ放送や配信がある大会では、賞金以外にメディア出演料や出演による副次的な収入を得る選手もいます。特に、Eco-ChallengeはAmazon Prime Videoで配信されたことで世界的な注目を集め、参加チームには大きなプロモーション効果もありました。
とはいえ、これらはごく限られたトップ大会での話であり、アドベンチャーレース全体では賞金付きの大会はまだ少数派です。次の項目で、日本国内の状況を見てみましょう。
日本国内レースの賞金・景品例
日本で開催されているアドベンチャーレースは、基本的に賞金が出るケースは非常に少ないのが現状です。多くの大会では、順位ごとに表彰状やトロフィー、アウトドア用品などの景品が授与される形をとっています。
ただし、過去には例外もありました。たとえば「里山アドベンチャーレース(旧・若狭町アドベンチャーレース)」では、優勝チームに10万円の賞金が授与された年もあります。また、地方自治体が主催・共催に入っている大会では、地域特産品や観光券などを景品として用意しているケースも多く、金銭的な報酬は少なくても“思い出に残る副賞”が楽しめます。
また、初心者向けの短距離レースでは、順位に関係なく抽選でギアが当たるなど、参加すること自体に価値を持たせている大会もあります。こうした工夫によって、競争一辺倒ではないアットホームな雰囲気が作られているのも日本の大会の特徴です。
スポンサー契約で得られる収入の可能性
賞金以外でアドベンチャーレース選手が収入を得る方法の一つに、「スポンサー契約」があります。日本のトップチーム「イーストウインド」も、複数のアウトドアブランドや企業からスポンサーを受けており、ウェアや装備、遠征費用の支援を受けながら活動しています。
一般的に、スポンサー契約の内容は「金銭的支援」と「物品提供」に分かれます。特に国内では、ギア提供(ウェア、バックパック、バイクパーツなど)が主で、金銭的サポートは一部のトップチームやメディア露出の多い選手に限られます。
選手側は、スポンサー企業の商品をSNSやブログで紹介したり、大会中の写真・映像でロゴを露出したりすることで、スポンサーに対する価値を提供しています。大会レポートやトレーニングの様子を発信することでファンを獲得し、ブランドイメージ向上に貢献できれば、継続的な支援が期待できます。
つまり、「競技の実力+情報発信力」が、スポンサーを得るための重要な要素となっているのです。
トップ選手の年収モデルとリアルな生活
アドベンチャーレースは、他のプロスポーツと異なり、それ単体で生活できる選手は非常に限られています。世界的に活躍するトップチームの選手でも、年収の大半は本業(会社員やアウトドアガイドなど)に依存しており、アドベンチャーレース単体で生計を立てている選手はごくわずかです。
たとえば、ARWSの上位チームの選手でも、レースの遠征費用をクラウドファンディングや個人負担で賄っているケースが多く、賞金だけで年間の活動費をまかなうことは現実的ではありません。
日本でも同様に、アドベンチャーレースを続けている人の多くは、平日は会社員として働きながら、週末にトレーニングや大会に参加しています。中には地方移住して自然環境の近くで生活しながら、アウトドア関連の仕事と両立して活動している選手もいます。
つまり、アドベンチャーレースは「生活のための仕事」ではなく、「人生を豊かにするための活動」として捉えられているケースが多いのです。
「好き」と「稼ぐ」は両立できるのか?
アドベンチャーレースで「好き」と「稼ぐ」を両立するのは、現時点では簡単ではありません。ただし、完全に不可能というわけでもなく、工夫次第で可能性は広がっているというのが実情です。
たとえば、YouTubeやSNSでの発信を通じて自分自身をブランド化し、企業からスポンサーを得る人もいれば、講演活動やナビゲーション講座、アウトドアイベントの主催などで収入を得ている選手もいます。アウトドア専門メディアに寄稿したり、ギアレビューを書いたりすることで、アスリートとしての活動と情報発信を組み合わせて収益を上げることも可能です。
また、アドベンチャーレースそのものではなく、「その知識・経験」を活かした仕事に転用する人もいます。ガイド業、教育活動、地方創生プロジェクトなど、アドベンチャーレースのスキルはさまざまな分野で応用が利きます。
つまり、「好きなことをして生活する」ためには、「どうお金を生む仕組みを作るか」がカギになります。競技の成績だけに頼るのではなく、自ら情報を発信し、人とつながり、価値を届けていく——そんな姿勢が、アドベンチャーレースを続けながら収入を得る道を拓くのです。
「クレイジージャーニー」で取り上げられた名場面
TBSの人気番組『クレイジージャーニー』は、アドベンチャーレースという競技を一般に知らしめたきっかけとなったメディアのひとつです。特に、日本代表チーム「イーストウインド」に密着した回は、多くの視聴者に強烈な印象を与えました。
番組では、リーダー田中正人さんが率いるチームが、世界選手権の過酷なコースに挑む様子を丁寧に追い、壮絶な山岳地帯や泥まみれのカヤック、寝不足と極限疲労に耐える姿がリアルに描かれました。なかでも、仲間の体調不良やルートミスを全員でカバーしながら前進するチームの姿は、「スポーツというより、人生そのものだ」と視聴者の心を打ちました。
この放送を通じて、「アドベンチャーレース=ただのレースではなく、極限での人間ドラマ」だと多くの人に伝わり、競技の魅力が大きく広まったのです。再放送や配信があれば、ぜひチェックしてほしい貴重なドキュメンタリーの一つです。
YouTubeで見られる本格レース動画5選
最近ではYouTube上にもアドベンチャーレース関連の動画が多数公開されており、観るだけでもスリルや感動を味わうことができます。中でもおすすめのコンテンツは以下の5つです。
- GODZONE(ニュージーランド)公式チャンネル
息をのむ絶景の中での超長距離レース。ドローン映像が美しく、初心者にも見やすい編集。 - ARWS(Adventure Racing World Series)公式動画
世界各国での予選・本選のダイジェストが揃っており、選手のインタビューや舞台裏も収録。 - Eco-Challenge Fiji 2019 ダイジェスト
Amazonの配信とは別に、公式YouTubeでは短編ハイライトが公開。サバイバル色が強めで刺激的。 - イーストウインド公式チャンネル
田中正人さん率いる日本代表の活動報告や大会の舞台裏を視聴可能。字幕付きで見やすい。 - Team KATANA Adventureのレース記録
日本人チームの等身大の挑戦がリアルに描かれ、初心者にも共感しやすい内容。
これらの動画を通じて、アドベンチャーレースの「現場感」や「レースの流れ」「ナビゲーションの重要性」などを直感的に理解することができます。
書籍・漫画・ドキュメンタリーのおすすめ
アドベンチャーレースをさらに深く知りたい人には、書籍やドキュメンタリーの活用もおすすめです。以下は特に評価の高いコンテンツです。
- 『限界のその先へ イーストウインドの冒険』(田中正人 著)
日本代表チームの長年の挑戦がつづられた名著。初心者にも読みやすく、感動必至。 - 『Eco-Challenge: The Expedition Race』(映像作品)
かつてDiscovery Channelで放送されていた、伝説的なドキュメンタリーシリーズ。 - 『Adventure Racing: The Ultimate Guide』(海外書籍)
英語ですが、戦術や装備、トレーニング方法まで網羅されており実践的な内容。 - 『TEAM EAST WINDレポートブック』
イーストウインド公式サイトなどで頒布されている記録集。写真・マップも豊富。
日本語で読めるコンテンツは少ないものの、田中正人さん関連の書籍やブログは質が高く、アドベンチャーレースの精神に触れられる貴重な教材となっています。
世界の有名選手をSNSでフォローしよう
世界中にはアドベンチャーレース界で活躍するトップ選手が多く、彼らはSNSを通じてトレーニング、遠征、日常の気づきなどを発信しています。フォローしておけば、モチベーションアップにもつながります。
- Nathan Fa’avae(ネイサン・ファバエ)
ニュージーランドのレジェンド。多くの世界大会を制しており、チームAvayaの中心人物。 - Emma Roca(エマ・ロカ)
故人ですが、女性アスリートとしてAR業界に革命をもたらした存在。今でも多くの人に影響を与えています。 - 田中正人(Masato Tanaka)
日本代表チーム「イーストウインド」リーダー。InstagramやXで日々の練習・遠征を投稿中。 - ARWS公式アカウント
世界各地の大会情報がリアルタイムで発信されており、新しいレースや注目チームがチェックできます。
SNSを活用することで、世界中のレースの空気感や、選手のリアルな思考に触れることができ、自分の競技への取り組みにも役立つでしょう。
観戦イベント・ボランティア参加の楽しみ方
アドベンチャーレースは「参加する」だけでなく、「観る・支える」ことでも楽しむことができます。実際に大会では、観戦可能エリアや応援スポットが設けられている場合があり、選手たちを間近で見ることができるのです。
特におすすめなのが、「ボランティアスタッフ」として大会運営に参加する方法です。大会前の準備や当日の受付、チェックポイントでの誘導など、さまざまな形でレースに関わることができます。運営スタッフとして携わることで、コース設計や安全対策、選手の苦労などを肌で感じることができ、将来的に自分が出場する際の大きな学びになります。
また、一部の大会では「ナビゲーター講座」「初心者説明会」など、観戦ついでに学べるプログラムも用意されており、体験型イベントとしても楽しめます。応援に行く家族や友人も含めて、アドベンチャーレースの世界に触れるきっかけとして最適です。
「まだ出る勇気はないけど、雰囲気を知りたい」という方は、まずは観戦やボランティアから始めてみるのも大いにアリです。
まとめ
アドベンチャーレースは、「体力」「知力」「チームワーク」「サバイバル力」が試される、究極のアウトドアスポーツです。山や川、森などの自然を舞台に、複数の種目をこなしてゴールを目指すこの競技は、一見すると超人しかできないようなイメージを持たれがちですが、実は日本国内でも初心者向けのレースが多数開催されており、誰でも挑戦できる環境が整ってきています。
テレビ番組『クレイジージャーニー』の影響で認知度も少しずつ高まりつつあり、日本にも「イーストウインド」のような世界に挑むチームが存在しています。最近では、新しい日本人チームの登場や地方自治体との連携による大会開催、SNSによる情報発信など、未来につながる動きも増えてきました。
装備や費用、仲間探しなど、最初は不安なことも多いですが、ミニレースや観戦、ボランティアから一歩踏み出すことで、人生が変わるような冒険が待っているかもしれません。アドベンチャーレースは「ただのスポーツ」ではなく、「生き方」そのものを問う体験です。さあ、あなたも一歩を踏み出してみませんか?