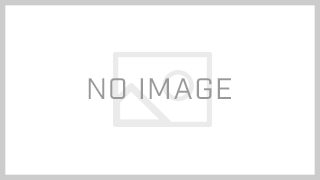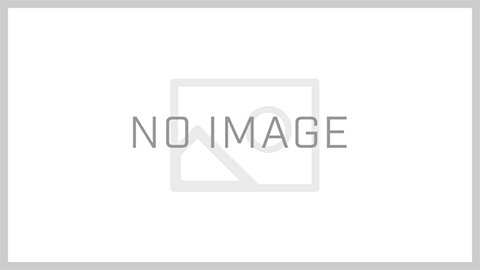古墳と聞いて、どんなイメージを持ちますか?
「歴史の授業で習った昔の墓」「あまり身近じゃないかも」と感じる方も多いかもしれません。けれど実は、奈良県には全国でも有数の古墳スポットが集まっており、観光やお散歩感覚で気軽に楽しめる場所がたくさんあるのです。
本記事では、奈良県に古墳が多い理由から、初心者におすすめの古墳スポット、深掘り型の楽しみ方、さらには古墳巡りのコツや訪問後の楽しみ方まで、たっぷりご紹介します。
歴史が苦手な方でも大丈夫!中学生でもわかるやさしい文章で、古代のロマンを感じる旅にあなたをご案内します。
さあ、現代から一歩タイムスリップして、静かにたたずむ古墳たちに会いに行きませんか?
奈良県に古墳が多い理由と基本を知ろう
古墳時代の概要と奈良県の位置づけ
古墳時代とは、3世紀中頃から7世紀頃までの日本の歴史区分で、この時代の特徴的な文化のひとつが「古墳」です。古墳とは、有力者や王などの権力者を葬るために築かれた巨大な墓で、その大きさや形、埋葬品などから当時の政治や社会構造が読み取れる重要な遺跡です。この古墳時代の始まりとされるのが、西暦250年ごろ。まさに日本の国家形成が始まりつつあった時代です。
この古墳時代の中心的な地域が「奈良県」なのです。奈良盆地を中心に、前方後円墳と呼ばれる巨大な古墳が次々と築かれ、日本最古の王権とされる「ヤマト王権」がここで誕生したと考えられています。ヤマト王権とは、後の天皇家につながる政権で、当時の有力豪族をまとめ、全国的な勢力を広げていくために、各地に支配の証として古墳を築かせました。
奈良はそのヤマト王権の本拠地であり、中心地として政権の核を担っていたため、自然と大王(後の天皇)やその家臣、大豪族たちの墓が集中したのです。実際に、全国の天皇陵のうち約4分の1が奈良県に存在するとされており、これは他県と比べても群を抜いて多い数です。
奈良県はまた、地形的にも古墳づくりに適した広い盆地を持ち、気候も穏やかで人の集まりやすい土地柄だったことも、古墳が集中した理由のひとつとされています。古墳時代を通して、奈良は政治・宗教・文化の中心地であり続け、それが現在までに残る古墳群の多さへとつながっているのです。
さらに注目すべきは、奈良県の古墳は保存状態が良好であること。国や県によってしっかりと管理されており、現地で実際に古墳を見学できる施設や遊歩道が整備されている場所も多く、歴史ファンだけでなく観光客にも親しまれています。
つまり、奈良県は古墳時代を知る上で欠かせない場所であり、まさに「古墳の聖地」と言えるでしょう。
古墳の主要な形(前方後円墳・円墳・方墳)
古墳とひとくちに言っても、その形にはいくつかの種類があります。代表的なものが「前方後円墳」「円墳」「方墳」の3つです。これらの形は、被葬者の地位や築造された時代、地域の文化によって異なりますが、奈良県内でもそのバリエーションを数多く見ることができます。
まず「前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)」は、古墳時代を象徴する形で、最も格式が高いとされる形式です。前から見ると、台形のような「前方部」と、その後ろに丸い「後円部」がくっついたカギ型のような独特の形をしています。この形式の古墳は3世紀中頃から6世紀頃にかけて築かれ、主にヤマト王権の中心人物や有力豪族の墓に使われました。奈良県では「箸墓古墳」や「西殿塚古墳」などが有名です。
次に「円墳(えんぷん)」は、文字通り円形の墳丘を持つ古墳で、古墳の中でも最も一般的な形式です。前方後円墳に比べると小規模なものが多く、地方の豪族や中級階層の支配者層に多く用いられました。また、時代が下ると王族にも円墳が使われるようになり、実は天皇陵でも後の時代になると円墳形式のものが多くなっています。
「方墳(ほうふん)」は、墳丘が四角形の古墳です。円墳と同様に、地方の豪族の墓として多く用いられ、奈良県内でも確認されています。方墳は初期の古墳によく見られ、前方後円墳よりもさらに古い形式とも言われていますが、実際には時代を問わず様々な場面で使われていました。
このように、古墳の形を観察することで、その墓がどのような人物のもので、いつ頃築かれたのかを推測する手がかりになります。特に奈良県の古墳群は、前方後円墳をはじめ多種多様な形式が揃っており、現地を訪れて直接その形を目にすることで、より深く古代の日本社会を感じることができます。
また、現代ではドローンや上空からの撮影によって古墳の形がはっきりと確認できるようになっており、これも見学の楽しみのひとつになっています。形の違いを意識して古墳を見て回ると、まるで歴史のパズルを解いているかのような感覚が味わえるでしょう。
なぜ奈良県に古墳が集中しているのか
奈良県には、日本全国でも群を抜いて多くの古墳が存在します。なぜこれほどまでに古墳が集中しているのでしょうか。その答えは、奈良が日本の古代国家形成における「中心地」だったからです。
古墳時代、日本の初期政権である「ヤマト王権」が奈良盆地を中心に成立しました。これは、現在の天皇制にもつながる統治体制の始まりであり、当時の有力豪族たちが結びついて形成された政治連合でした。この王権の中核にいた支配者たちは、自分たちの権力の大きさを象徴するために、巨大な墓である古墳を築くことが重要だと考えていました。
奈良は、そのヤマト王権が誕生し、成長していった本拠地です。自然と政治的にも宗教的にも重要な人物たちがこの地に集まり、彼らのために築かれた古墳が集中していくのは、ある意味当然の流れといえます。特に奈良県の桜井市や明日香村、天理市などには、3世紀〜7世紀に築かれた多数の前方後円墳や古墳群が残されており、それぞれが当時の勢力図を映し出す鏡ともいえる存在です。
さらに地理的な条件も奈良を古墳の集中地にした理由のひとつです。奈良盆地は周囲を山に囲まれた平坦な地形であり、農業がしやすく人口が集中しやすい場所でした。また、石材や土の採取が容易で、古墳築造に適した土地でもありました。これらの条件が、政治と生活の中心を奈良に集中させ、結果的に古墳の建造もこの地域に偏ったという背景があります。
加えて、奈良には「陵墓参考地」と呼ばれる天皇や皇族の墓が今でも数多く存在しています。宮内庁が管理しているこれらの場所は、発掘調査などが制限されていますが、それだけに“特別な場所”として今も神聖視されており、古代から現代まで歴史が連続していることを実感させてくれます。
現在確認されている奈良県内の古墳は数百基にのぼり、未発見や未確認の古墳を含めれば、さらにその数は多いとされています。これだけの規模で古墳が残されている地域は日本全国を見ても非常に稀です。まさに奈良県は「古墳の宝庫」と言える存在であり、歴史に興味のある人にとっては、見逃せないスポットとなっています。
古墳を見る楽しみポイント(歴史・景観・遺構)
古墳を見るという行為は、ただ古いお墓を見るだけではありません。実際に奈良県の古墳を訪れると、そこには古代人の生活、思想、そして権力のあり方が垣間見える、まさに“時空を超えた旅”のような体験が広がっています。ここでは、古墳を見る際に注目したい楽しみ方を3つの視点から紹介します。
まずは「歴史的な背景」です。古墳は3世紀から7世紀にかけて作られたもので、それぞれの古墳には築造された年代、被葬者の身分や政治的立場など、重要な歴史情報が詰まっています。たとえば、奈良県の箸墓古墳は「卑弥呼の墓ではないか」とする説もあり、日本古代史の謎とロマンを感じることができます。また、石舞台古墳は、飛鳥時代の有力者・蘇我馬子の墓と考えられており、実際に石室内部まで入れる貴重な古墳です。こうした背景を知ってから現地を訪れると、その古墳が“生きた歴史資料”に見えてくるでしょう。
次に「景観」です。古墳は山や丘、田園地帯に点在しており、その場所そのものが美しい景観スポットになっていることが多いです。奈良盆地の自然と調和するように築かれた古墳の姿は、まるで風景の一部として存在しているかのようです。特に、馬見丘陵公園にある古墳群では、季節ごとに咲く花々と古墳が一体となった絶景が楽しめます。春は桜、夏は蓮、秋にはコスモスなど、四季折々の自然の中で歴史に触れる贅沢な時間が過ごせます。
最後は「遺構」です。古墳そのものが遺構ですが、中には石室内部に入れるものや、発掘された出土品を展示する資料館が隣接している場所もあります。たとえば、黒塚古墳では33枚の三角縁神獣鏡(中国由来の鏡)が出土し、現在は隣接する展示館で実物を見学できます。キトラ古墳では、四神(青龍・白虎・朱雀・玄武)の壁画が発見され、保護された一部が公開されることもあります。古墳はただの“盛り土”ではなく、そこに眠る副葬品や石組み、構造などが、当時の人々の死生観や文化を語ってくれるのです。
このように、古墳巡りは歴史・景観・遺構という3つの視点から楽しむことができます。しかも、奈良県の古墳の多くは無料で公開されており、整備された遊歩道や案内板もあるため、初心者でも安心して訪れることができます。自分のペースで散策しながら、数千年前の人々に思いを馳せる——それが古墳巡りの最大の魅力です。
古墳巡りのマナー・注意点
奈良県の古墳は、日本の歴史を肌で感じられる貴重な文化財であり、現在も多くの人々に親しまれています。しかし、古墳は単なる観光スポットではなく、かつて人が葬られた「お墓」であるという側面を忘れてはいけません。古墳巡りをより深く、かつ気持ちよく楽しむためには、いくつかの基本的なマナーや注意点を知っておくことが大切です。
まず第一に、「立ち入り禁止区域には入らない」こと。多くの古墳には宮内庁によって管理されている陵墓(りょうぼ)や陵墓参考地が含まれており、そこは原則として立ち入りが制限されています。たとえば、箸墓古墳やホケノ山古墳などは柵の外からの見学のみが許可されています。柵を越えたり、無断で内部に入ったりすることは絶対に避けましょう。古墳を守るためにも、ルールを守った見学が必要です。
次に、「植物や土に触れない・採取しない」ことも大切です。古墳は自然と調和した景観の中にありますが、木々や草花、土壌は歴史的環境の一部でもあります。これらを傷つけたり、持ち帰ったりする行為は文化財保護の観点からもNGです。また、石垣や埴輪(はにわ)など、現地に設置されたものには決して触れないようにしましょう。
「騒音を出さない」ことも、古墳巡りの基本的なマナーのひとつです。古墳の多くは静かな場所にあり、他の来訪者や地元の人たちの迷惑にならないように配慮が必要です。スピーカーを使って音楽を流したり、大声で会話をしたりするのは控えましょう。また、神社などと併設されている場所では、参拝の作法にも注意したいところです。
「ゴミは持ち帰る」という意識も忘れてはなりません。古墳の周囲にはゴミ箱が設置されていない場合が多く、自分のゴミは必ず持ち帰るようにしましょう。飲食をする際は場所を選び、食べかすや容器などをそのまま放置しないようにするのが、次に来る人へのマナーでもあります。
最後に、「写真撮影」についての注意です。古墳の外観を写真に収めることは可能な場所が多いですが、フラッシュの使用を控えるべき場所や、ドローンの使用が禁止されている区域もあります。特にキトラ古墳や高松塚古墳など、壁画や出土品に関する施設では撮影禁止のエリアもあるため、案内板や係員の指示には従いましょう。
このように、古墳巡りには最低限のルールとマナーを守ることが求められます。文化財を大切にし、後世に伝えるためにも、一人ひとりが意識をもって見学することが何よりも重要です。正しいマナーで古墳を訪れることで、より深く歴史と向き合い、静かな感動を味わうことができるでしょう。
初めての古墳巡りにおすすめのスポット3選
箸墓古墳(桜井市)
奈良県桜井市にある「箸墓古墳(はしはかこふん)」は、古墳ファンのみならず、日本の歴史に興味のあるすべての人におすすめしたい古墳です。全長は約280メートルにもおよぶ巨大な前方後円墳で、古墳時代初期(3世紀中頃)に築かれたとされ、日本最古級の前方後円墳として知られています。築造年代や規模、被葬者の有力説など、あらゆる面で日本史における重要な位置を占める存在です。
箸墓古墳は、その名の通り「箸が突き刺さったような形」に見えるという伝説から名づけられたとも言われていますが、一般的には『日本書紀』や『古事記』に登場する卑弥呼の墓ではないかという説が根強く残っています。実際に、宮内庁によって第7代孝霊天皇の皇女・倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)の陵墓として治定されており、その神秘性からも多くの人の興味を引きつけています。
残念ながら、箸墓古墳は宮内庁が管理する陵墓であるため、墳丘に登ったり石室内部を見学したりすることはできません。しかし、周囲には遊歩道が整備されており、外周を歩きながらその巨大な姿を間近で感じることができます。特に古墳の南側には池があり、水面に映る古墳の姿は非常に美しく、訪れる人々を魅了します。春には桜、秋には紅葉が見られ、四季折々の景色とともに楽しめるのも大きな魅力です。
また、古墳のすぐ近くには「大神神社(おおみわじんじゃ)」があり、古墳巡りと合わせて神社参拝もできます。大神神社は日本最古の神社のひとつとされ、箸墓古墳との関連も深い場所です。このように、箸墓古墳は単なる遺跡としてではなく、日本神話や古代史、宗教的背景までも感じさせてくれる特別な場所なのです。
アクセスも比較的良好で、JR桜井線の巻向(まきむく)駅から徒歩約10分程度と、電車でも訪れやすいのが嬉しいポイント。周辺には無料の駐車場もあり、車でのアクセスも可能です。初めての古墳巡りにぴったりのスポットとして、ぜひ訪れてみてください。
石舞台古墳(明日香村)
奈良県高市郡明日香村にある「石舞台古墳(いしぶたいこふん)」は、日本で最も有名な古墳のひとつです。特徴はなんといってもその巨大な石室で、天井石を含む総重量は約2,300トンにもなると言われています。現在は盛土が失われているため、石室がむき出しになっており、古墳時代の内部構造を間近に見学できる極めて貴重な場所です。
石舞台古墳は、飛鳥時代(7世紀初め)に築かれた横穴式石室の古墳で、被葬者は明確には特定されていませんが、有力な説として「蘇我馬子(そがのうまこ)」が葬られた墓ではないかとされています。蘇我馬子は飛鳥時代の有力豪族で、仏教の受容や政治改革に深く関与した歴史的キーパーソンです。こうした背景もあり、石舞台古墳は単なる遺跡にとどまらず、日本史の一大転換期を象徴するスポットとして注目されています。
この古墳の大きな魅力のひとつは、石室内部に実際に入ることができる点です。日本の多くの古墳は、内部が非公開だったり、宮内庁の管理下で立ち入りが制限されていたりしますが、石舞台古墳は例外的に見学が可能で、誰でも自由に石室の中に入って見学することができます。巨大な石が積み上げられてできた空間は圧巻で、当時の土木技術の高さを実感できるとともに、古代の死生観や権力の大きさを肌で感じることができる場所です。
また、石舞台古墳の周辺は「国営飛鳥歴史公園 石舞台地区」として整備されており、広々とした芝生や季節の花々が楽しめるエリアとしても人気です。古墳を中心に、家族連れやカップルがゆったりと過ごせるような観光地になっており、歴史好きだけでなくピクニックや散歩を楽しみたい人にもおすすめです。春には桜、秋には紅葉の名所としても知られています。
アクセスも良好で、近鉄飛鳥駅から徒歩約25分、またはレンタサイクルを利用してのアクセスも可能です。現地には観光案内所やカフェ、休憩スペースもあり、初心者でも安心して楽しめる観光地となっています。入場には有料(大人300円、中学生以下100円)ですが、石室に入れる体験はそれ以上の価値があると言えるでしょう。
古墳巡りのスタートとしてはもちろん、古代史に触れる第一歩としても非常におすすめのスポットです。
キトラ古墳(明日香村)
奈良県明日香村にある「キトラ古墳(キトラこふん)」は、7世紀末から8世紀初頭に築かれたとされる小規模な円墳ですが、日本の古墳史の中でも極めて重要な位置を占める遺跡です。最大の特徴は、石室の内部に描かれた色鮮やかな「壁画」です。キトラ古墳の発見により、それまでの古墳観を大きく塗り替えるほどの衝撃がもたらされました。
この古墳が広く知られるようになったのは、1983年に内部から「四神図(しじんず)」と呼ばれる壁画が確認されたことがきっかけでした。四神とは、東の青龍、南の朱雀、西の白虎、北の玄武という中国の思想に基づいた神獣で、それぞれの方角を司る守護神とされています。これらが精緻な筆致で描かれていたことから、当時の日本が中国や朝鮮半島の高度な文化と交流していたことが分かります。
また、天井部分には天文図も描かれており、現存する日本最古の星図としても知られています。このような装飾古墳は日本では非常に珍しく、キトラ古墳と高松塚古墳の2例しか確認されていません。学術的価値が非常に高いため、内部の保存処理は慎重に行われており、現在も継続的な保存・修復が行われています。
一般公開については、直接石室内部に入ることはできませんが、古墳のすぐ近くにある「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」で、実物大の石室模型や、壁画の高精細レプリカを鑑賞することができます。また、保存処理を終えた本物の壁画が一定期間だけ特別公開されることもあり、事前申込みによって間近で観覧できる貴重なチャンスとなっています。
キトラ古墳自体は小さな円墳で、直径はおよそ13.8メートル、高さ約3.3メートルとコンパクトですが、その中に詰まっている文化・技術・歴史は非常に深いものがあります。墳丘の周囲は遊歩道が整備されており、散策しながら古墳や周辺の自然を楽しむことも可能です。特に展望台からの景色は絶景で、飛鳥の里山風景とともに、古代への想像をかき立てられるスポットとなっています。
アクセスも良好で、近鉄飛鳥駅からレンタサイクルや明日香周遊バスを使えば、他の古墳と合わせて効率よく回ることができます。歴史ファンだけでなく、アートや宇宙に興味がある方にもおすすめの古墳です。
各スポットの訪問時間・服装のポイント
奈良県の古墳巡りを楽しむうえで、実際に「いつ行くか」「どんな服装で行くか」という点はとても大切です。古墳は自然の中にあることが多く、季節や時間帯、天候によってその魅力が大きく変わります。また、見学中の快適さや安全にも関わるため、事前にしっかりと準備しておくことで、より満足度の高い古墳巡りができます。
まず、訪問時間についてです。古墳は基本的に屋外にあり、多くは公園や史跡として自由に散策できますが、資料館や入場制限のある施設は営業時間が決まっています。たとえば、石舞台古墳は年中無休で公開されていますが、開園時間は通常午前8時30分〜午後5時までとなっており、入場は閉園の30分前までです。キトラ古墳に併設された「四神の館」も午前9時から午後5時まで開館しています。
午前中に訪れると、観光客が比較的少なく、落ち着いて見学できます。特に夏場は午前中の方が気温がまだ上がりきっておらず、快適です。また、秋や冬は日没が早いため、午後の訪問では暗くなってしまうこともあります。午前中からお昼過ぎにかけての時間帯が、もっとも安心して楽しめるゴールデンタイムです。
次に、服装についてです。古墳の多くは自然の中にあり、舗装されていない道や階段、ゆるやかな丘を歩く必要がある場所も少なくありません。そのため、動きやすい服装と、歩きやすい靴が基本です。特にスニーカーやトレッキングシューズがおすすめです。夏場は帽子・サングラス・日焼け止め、冬場は防寒具と手袋があると安心です。春や秋は朝晩と日中の気温差があるため、軽い上着やパーカーを持参すると便利です。
また、雨が降るとぬかるみやすい場所もあるため、雨天時はレインコートや撥水性のある上着、防水スニーカーが重宝します。傘よりも両手が空くレインポンチョや帽子付きのジャケットのほうが安全かつ便利です。加えて、虫よけスプレーや飲み物、簡単な救急セットもあると安心して楽しめます。
さらに、レンタサイクルを利用する場合は風を切って移動するため、体感温度が下がります。防風ジャケットやグローブがあると快適に回ることができます。女性の場合はヒールのある靴やスカートは避け、パンツスタイルが動きやすくおすすめです。
季節の花と古墳を楽しめる馬見丘陵公園や、田園風景に溶け込む箸墓古墳など、自然との調和を体感できるのも奈良県の古墳巡りの魅力です。その場を存分に味わうためにも、天候と服装への準備は抜かりなく行いましょう。
写真撮影で押さえておきたい構図・ポイント
奈良県の古墳を訪れたら、やはり写真に収めておきたくなるものです。特に広大な自然の中にたたずむ古墳は、まるで古代からのメッセージが込められているかのような神秘的な美しさを持っています。しかし、ただシャッターを押すだけでは、その魅力はなかなか写りきりません。ここでは、古墳をより印象的に撮るための構図やポイントをいくつかご紹介します。
まず意識したいのは、「遠景と近景のバランス」です。古墳はその規模や形が重要な要素のひとつなので、できるだけ全体像が収まる構図で撮影することが大切です。たとえば、箸墓古墳では南側の池越しに撮影すると、水面に映る墳丘がとても美しく、左右対称のバランスも良い1枚が撮れます。前方後円墳の独特な形は、高台や遠景からの撮影でより強調されるため、撮影場所を少し離れて探すのがポイントです。
次に、季節の植物や自然と古墳を一緒に撮ることで、写真に深みが生まれます。春の桜、夏の緑、秋の紅葉、冬の枯木と空――それぞれの季節でまったく違った雰囲気の古墳が撮影できます。特に馬見丘陵公園のように四季折々の花と古墳が調和するスポットでは、花を前景に入れて古墳を背景にする構図が人気です。被写体の手前に草木を入れることで、奥行きのある写真が撮れるのでおすすめです。
また、石舞台古墳のような石室に入れる古墳では、「中から外を見る」構図も非常に面白いです。石の重厚感や光の差し込みを生かして撮ると、神秘的でドラマチックな1枚になります。スマートフォンでもHDR機能やナイトモードを使えば、暗い石室内でも美しく撮影できます。石の質感を強調したい場合は、光と影のコントラストを意識するとよいでしょう。
撮影マナーにも注意が必要です。ドローンの使用は禁止されている場所が多いため、必ず現地の案内板やルールを確認してください。また、三脚や自撮り棒の使用が制限されている場合もあるので、周囲の状況に配慮しながら撮影しましょう。人気の少ない早朝や夕方は、他の来訪者の迷惑にならず、ゆっくりと撮影を楽しめる時間帯でもあります。
最後に、写真にひと工夫加えたい場合は「人物を入れる」構図も効果的です。遠近感を出すことで古墳の大きさが際立ち、旅の記録としても印象に残る1枚になります。ただし、人物が主役になりすぎないように、バランスを意識して撮影しましょう。
このように、奈良の古墳は歴史を感じるだけでなく、カメラ片手にアートとしても楽しめる魅力的な被写体です。ぜひ、自分だけの“古墳の一枚”を探してみてください。
確かな情報がある “もう一歩踏み込んだ古墳巡りスポット”
黒塚古墳(天理市)
奈良県天理市柳本町にある「黒塚古墳(くろづかこふん)」は、古墳ファンはもちろん、歴史に興味のある一般の方にもおすすめできる“深掘り型”の古墳スポットです。この古墳は全長約130メートルの前方後円墳で、4世紀末〜5世紀初頭に築造されたと考えられています。1997年に行われた発掘調査で、多数の副葬品が発見されたことで一躍注目されるようになりました。
最大の特徴は、なんといっても33面もの「三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)」が出土したことです。三角縁神獣鏡とは、縁が三角形に盛り上がっており、鏡の裏面に神獣や神仙の姿が鋳出された銅鏡の一種で、中国・魏の時代の文化的影響を受けたものとされています。これだけの数がまとまって出土した例は他になく、日本の古代史研究において非常に重要な資料とされています。
黒塚古墳の魅力は、出土品の一部が隣接する「黒塚古墳展示館」で実際に見られる点です。展示館は無料で公開されており、出土した鏡のレプリカや、墳丘の復元模型、当時の埋葬方法に関する解説などが分かりやすく展示されています。小さな施設ながらも非常に質が高く、知識がなくても楽しめるように工夫されています。子ども連れのファミリーや修学旅行のコースにも組み込まれており、教育的な価値も高いスポットです。
また、黒塚古墳は墳丘への立ち入りが可能で、実際に登ってその形状や規模を体感することができます。周囲は静かな住宅街にあり、落ち着いた雰囲気の中でゆっくりと散策することができるのもポイント。古墳全体を見渡せる場所も整備されており、前方後円墳の特徴的な形を確認しながら歩くことができます。
アクセスについても便利で、JR万葉まほろば線(旧・桜井線)の「柳本駅」から徒歩5分ほどと、公共交通機関でも気軽に訪れることができます。周辺には「崇神天皇陵」や「景行天皇陵」とされる巨大古墳も点在しており、“古墳密集エリア”として知られる柳本エリアの拠点にもなっています。
古墳巡りに少し慣れてきた方にとって、黒塚古墳は「発掘と出土品」「学べる展示館」「歩いて楽しめる古墳」の三拍子がそろった理想的なスポットです。手軽ながらも本格的に古代史のロマンに浸れる、まさに“一歩踏み込んだ”体験をしたい方にぴったりの場所と言えるでしょう。
馬見古墳群(香芝市・広陵町・河合町)
馬見古墳群(うまみこふんぐん)は、奈良県の香芝市・広陵町・河合町の3市町にまたがる広大な古墳群で、総数は160基以上、規模としては全国屈指の大古墳密集地帯です。最大の特徴は、古墳だけでなく自然公園として整備されており、古墳巡りとレジャーの両方を楽しめる点にあります。
馬見古墳群には、5世紀から6世紀にかけて築造された前方後円墳、円墳、方墳などが点在しており、「巣山古墳」「ナガレ山古墳」「乙女山古墳」などが代表例です。これらの古墳の多くは大王(おおきみ)に仕えた地方豪族の墓と考えられており、ヤマト王権の支配構造を示す貴重な遺跡群として注目されています。
この古墳群の魅力は、奈良県営「馬見丘陵公園」として見事に整備されていることです。公園内は広大な芝生広場、花の名所、遊歩道、カフェ、展望台などがあり、まるで都市公園のような快適な空間になっています。春にはチューリップ、夏にはひまわり、秋にはコスモスが咲き誇り、古墳と花の共演を楽しめる珍しい観光地です。
また、馬見古墳群には古墳の上に登れるスポットや、墳丘を間近で見学できる場所もあります。学術的に重要なだけでなく、誰でも気軽に楽しめる「開かれた古墳」として地元住民にも親しまれています。
アクセスは近鉄田原本線「池部駅」や「箸尾駅」から徒歩圏内。公園には駐車場も整備されており、ファミリーや観光客にとっても非常に訪れやすい環境が整っています。
スポット選び:古墳群 vs 単体古墳の楽しみ方
奈良県には、石舞台古墳のような「単体で目立つ古墳」と、馬見古墳群のような「古墳が集まっているエリア」の両方が存在しています。それぞれに異なる魅力があり、どちらを選ぶかによって古墳巡りのスタイルも変わります。
単体古墳の魅力は、その“迫力”と“集中体験”です。石舞台古墳のように石室内に入れるスポットでは、古墳そのものをじっくり体験でき、構造や歴史背景に深く入り込めます。また、箸墓古墳のような格式のある古墳は、周囲の神話や伝承とセットで楽しむことができます。
一方、古墳群は「数で勝負」です。馬見古墳群や柳本古墳群などは、一帯に複数の古墳が点在しており、地図を片手に散策しながら次々と古墳を発見する楽しさがあります。古墳ごとの形状や規模を比較しやすく、歩くたびに新たな発見があるのが魅力です。家族連れやウォーキングを楽しみたい方には、古墳群が向いているでしょう。
また、古墳群には公園や休憩所、季節の花が楽しめるスポットも併設されている場合が多く、歴史+レジャーの組み合わせが可能です。逆に、単体古墳はその古墳に集中できる反面、1カ所での滞在時間が短くなりがちです。自分の興味や旅の目的に合わせて、「深く知りたい」なら単体、「楽しく巡りたい」なら古墳群、というように選ぶとよいでしょう。
季節・時間による楽しみ方の違い
奈良の古墳は四季折々の自然とともに楽しめるのが大きな魅力です。古墳と自然の風景を一緒に味わうことで、訪問の満足度はさらに高まります。どの季節に行ってもそれぞれの良さがありますが、特におすすめなのが春と秋です。
春は桜のシーズン。箸墓古墳や石舞台古墳の周辺には桜並木があり、墳丘と満開の桜を一緒に写真に収めることができます。また、馬見丘陵公園ではチューリップフェアが開催され、色とりどりの花と古墳が織りなす絶景が楽しめます。
夏は新緑と花が魅力。ひまわりや蓮の花が咲く古墳群では、生命力を感じさせる風景が広がります。ただし、気温が高くなるため、午前中の訪問がおすすめです。
秋は紅葉の名所として知られる古墳も多く、石舞台古墳では周囲のもみじが色づき、美しいコントラストを楽しめます。空気が澄んでいて写真も美しく撮れるため、撮影を楽しみたい方に特に人気のシーズンです。
冬は人が少なく、静かに古墳と向き合える時期。空気が冷たいぶん、風景がはっきりと見え、晴れた日には青空とのコントラストが美しい写真が撮れます。
時間帯としては、朝〜午前中がおすすめです。観光客が少なく、光の角度も良いため、撮影にも最適です。逆光を避けたい場合は午後早めの時間帯に回ると良いでしょう。
古墳巡りで“マニアック”にならないためのポイント(無理せず楽しむ)
古墳巡りを深掘りしようとすると、ついつい情報収集や現地巡りに夢中になってしまいがちです。しかし、無理をしすぎると疲れてしまい、本来の楽しさを見失ってしまうことも。ここでは、古墳巡りを“マニアック”にしすぎず、誰でも楽しく続けられるポイントを紹介します。
まずは「数をこなすより、じっくり見る」ことが大切です。奈良には膨大な数の古墳がありますが、1日に何十基も見るのは現実的ではありません。1日2〜3カ所に絞り、資料館や現地解説を読みながらじっくり観察することで、理解も深まり、満足感も高まります。
次に、「行く前に少しだけ予習をする」のもおすすめ。完全な事前学習は不要ですが、その古墳がどの時代のもので、どんな特徴があるのかをざっくり把握しておくだけで、現地での感動が何倍にもなります。今はスマホで手軽に検索できるので、現地で情報を見ながら楽しむのも一つの方法です。
また、「全部を歩かずに、レンタサイクルやバスを活用する」ことも、疲れずに楽しむポイントです。特に明日香村や馬見古墳群のように広範囲に古墳が分布しているエリアでは、自転車移動が非常に便利です。体力に不安がある方は、エリアを限定した短時間コースも検討してみましょう。
そして何より、「自分のペースで楽しむ」ことが一番大切です。歴史に詳しくなくても、自然や風景を楽しむだけでも十分に価値があります。古墳は、学ぶだけでなく“感じる”遺跡でもあります。五感を使って、その場の空気を味わうことも古墳巡りの魅力のひとつです。
古墳巡りをもっと楽しむためのコツ
交通手段とアクセス
奈良県の古墳巡りをスムーズに楽しむには、交通手段の選択がとても重要です。古墳は点在している場所も多く、観光地として整備されている所もあれば、住宅地の中や山のふもとにひっそりとあるケースもあります。アクセス方法を事前に把握し、自分に合った移動手段を選ぶことで、無駄な移動時間を減らし、より多くの古墳を楽しむことができます。
まず、公共交通機関での移動について。主要な古墳スポットには近鉄電車やJRを使ってアクセスできます。たとえば、石舞台古墳やキトラ古墳がある明日香村へは、近鉄「橿原神宮前駅」や「飛鳥駅」からレンタサイクルや明日香周遊バスを使って巡るスタイルが一般的です。特に飛鳥駅前にはレンタサイクル店が複数あり、電動アシスト付き自転車も用意されているため、坂道の多いエリアでも安心して移動できます。
一方で、黒塚古墳や箸墓古墳など、天理市・桜井市周辺の古墳を巡る場合は、JR万葉まほろば線(旧・桜井線)を活用するのが便利です。駅から徒歩圏内に古墳がある場所も多く、初めての人にもわかりやすいルートになっています。
次に、マイカーでの移動も非常におすすめです。奈良県内の古墳スポットの多くには無料または有料の駐車場が整備されており、自分のペースで自由に移動できるのが魅力です。特に馬見古墳群や飛鳥エリアでは、複数の古墳を巡るには車の方が効率が良い場面が多くなります。
ただし、古墳によっては駐車場が小さかったり、住宅地に隣接していて車の進入が制限されていたりすることもあるため、事前にGoogleマップや公式観光サイトで情報を確認することが大切です。ナビに古墳名を入力しても表示されない場合があるため、「展示館」「史跡名」「駐車場名」で検索すると見つかりやすくなります。
アクセス手段をうまく使い分けることで、古墳巡りはより快適で充実した旅になります。グループ旅行なら車、個人や歴史散策メインなら電車+バス+自転車といった選択肢を組み合わせて、自分に最適な移動スタイルを見つけてください。
資料館・ガイド・展示を活用しよう
古墳巡りの楽しさを何倍にも深めてくれるのが、現地の資料館や展示施設の活用です。ただ「見る」だけでなく、歴史的背景や出土品、構造などを知ることで、目の前の古墳がぐっと身近に感じられるようになります。奈良県には古墳に関連した高品質な資料館が多数あり、誰でも気軽に立ち寄ることができます。
たとえば黒塚古墳に隣接する「黒塚古墳展示館」は入館無料で、出土した三角縁神獣鏡のレプリカや、墳丘の復元模型などを展示しています。小規模ながらも非常に内容が充実しており、古墳の内部構造や副葬品の意味などを視覚的に理解できます。
キトラ古墳のそばにある「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」では、四神図や天文図を再現した展示を間近で見学することができ、古代の宇宙観や美術に触れる貴重な機会となります。体験コーナーや映像解説も用意されており、小学生から大人まで楽しめる構成です。
さらに、「飛鳥資料館」「奈良県立橿原考古学研究所附属博物館」など、より専門的な施設では、奈良県全体の古墳文化を体系的に学ぶことができます。訪問の前後に立ち寄ることで、点と点がつながり、古墳巡りの理解が深まるでしょう。
ガイドサービスを利用するのもおすすめです。飛鳥地方では、地元ボランティアによるガイドツアーが定期的に行われており、申し込み制で古墳や寺社を巡ることができます。解説を聞きながら歩くことで、何気ない風景や小さな発見も意味のあるものに変わります。
このように、資料館やガイドは、古墳巡りを「体験」から「学び」へと昇華させてくれる強力な味方です。見て、聞いて、感じることで、あなたの中の古代ロマンがより深く刻まれるはずです。
周辺観光との組み合わせ
古墳巡りをさらに充実した旅にするには、周辺の観光地と組み合わせるのが効果的です。奈良県は古代日本の政治・宗教・文化の中心地であり、古墳と深いつながりをもつ神社や寺院、歴史的な街並みが数多く残されています。古墳を起点に、その背景や信仰を感じ取れるスポットを訪れることで、旅の満足度が格段にアップします。
たとえば、箸墓古墳のすぐ近くには「大神神社(おおみわじんじゃ)」があります。日本最古の神社のひとつとされ、背後の三輪山をご神体とする独特の信仰が今も息づいています。箸墓古墳と大神神社は神話的にもつながりがあり、古墳時代の宗教観を体感できる貴重なスポットです。
石舞台古墳がある明日香村周辺では、「飛鳥寺」や「高松塚古墳」「甘樫丘展望台」など、古代飛鳥文化に関わる見どころが点在しています。徒歩やレンタサイクルでゆっくり巡れる範囲にまとまっているため、歴史に触れながら自然も満喫できます。特に飛鳥の街並みは静かで落ち着いた雰囲気があり、都会の喧騒から離れて古代に思いを馳せるのにぴったりです。
また、天理市の黒塚古墳を訪れた後には、奈良市方面へ足を延ばして「東大寺」「春日大社」「奈良公園」などの有名観光地を訪れるのもおすすめ。天理から奈良市内までは電車で30分ほどの距離なので、日帰りでも十分に回れます。
このように、古墳とセットで楽しめる観光地をうまく組み合わせることで、単なる歴史散策を超えた“文化体験型の旅”を実現できます。事前に地図やルートを調べ、1日のスケジュールをゆったりと立てて、古墳+神社仏閣+カフェ巡りといった、自分好みのコースを作ってみてください。
写真・ドローン・SNS映えポイント
古墳巡りの楽しみ方として、SNSや写真撮影を重視する人も多いはず。奈良の古墳は、自然に囲まれたロケーションが多く、写真映えするスポットがたくさんあります。ここでは、誰でも簡単に“いい写真”が撮れるポイントと注意点をご紹介します。
まず、石舞台古墳は定番の撮影スポットです。露出した石室を正面から撮るのはもちろん、石室内に入って天井を見上げるアングルもおすすめです。光と影のコントラストが強調され、神秘的な雰囲気が演出できます。朝や夕方の斜光を狙うと、陰影がさらに深まり、美しい1枚が撮れます。
箸墓古墳では、南側の池越しに撮影する構図が人気です。特に風がない日の朝方、水面に古墳が映る“逆さ箸墓”が狙い目。春の桜や秋の紅葉と一緒に写すと、自然と古代の風景が調和した幻想的な写真になります。
馬見古墳群では、花と古墳の組み合わせが最大の魅力。チューリップやコスモスの咲くシーズンには、前景に花を入れたローアングル構図が映えます。花越しに墳丘をとらえることで、季節感と立体感が強調され、SNS映え間違いなしです。
一方、ドローン撮影に関しては注意が必要です。多くの古墳エリアではドローンの使用が禁止されています。特に宮内庁管轄の陵墓や、国の史跡に指定されている場所では、無許可の飛行は厳しく制限されています。必ず案内板や自治体の公式情報を確認し、ルールを守って撮影しましょう。
最近では「#古墳女子」「#古墳旅」などのハッシュタグを使ってSNSに投稿する人も増えており、古墳が新しいブームとして注目されつつあります。写真を通して、歴史の魅力をもっと多くの人と共有するのも、現代ならではの古墳巡りの楽しみ方と言えるでしょう。
子ども連れ・高齢者・歴史好きそれぞれの楽しみ方
古墳巡りは年齢や興味によって楽しみ方が大きく変わる旅のスタイルです。奈良県の古墳スポットは、誰でもアクセスしやすく、家族連れやシニア層、ディープな歴史ファンまで幅広く楽しめるように整備されています。ここではタイプ別のおすすめの楽しみ方を紹介します。
まず子ども連れには、広い公園内に古墳が点在する馬見丘陵公園や、体験型展示があるキトラ古墳「四神の館」がおすすめです。自由に走り回れる芝生広場、遊具、季節の花などもあり、ピクニック気分で古墳に親しめます。また、黒塚古墳展示館などでは子ども向けの展示解説もあり、学習旅行のような感覚で楽しめます。
高齢者や歩く距離が心配な方には、駐車場やベンチが充実しているスポットが安心です。石舞台古墳は石室までの道が整備されており、無理なく見学できます。また、飛鳥エリアには電動アシスト付き自転車のレンタルもあるので、坂道もラクに移動可能です。ゆったりした日程で、1〜2カ所をじっくり訪問するのが疲れにくくおすすめです。
歴史ファンには、黒塚古墳や箸墓古墳、キトラ古墳のように学術的価値の高いスポットが人気です。副葬品、壁画、古文献との関係など、事前に調べてから行くことで、現地での感動が何倍にもなります。また、飛鳥資料館や奈良県立橿原考古学研究所附属博物館などでの学びもセットにすると、知的好奇心を大いに満たしてくれるでしょう。
このように、古墳巡りは“誰でも楽しめる歴史の旅”です。無理なく、自分に合ったペースで、古代ロマンを体感してみてください。
訪問後に楽しみたいことと、次へのステップ
古墳巡り後に立ち寄りたいグルメ・カフェスポット
古墳巡りでたくさん歩いたあとは、ゆっくりと美味しいものを食べながら一息つきたくなるものです。奈良県は自然豊かで食文化も多彩な地域なので、古墳スポット周辺には地元ならではのグルメや雰囲気の良いカフェが点在しています。ここではいくつかの代表的なエリアごとに、立ち寄りやすい飲食店を紹介します。
まず、明日香村では「飛鳥鍋」や「にゅうめん」といった郷土料理を提供する食事処があります。地元野菜をふんだんに使った定食メニューが人気で、身体に優しく、歩き疲れたあとにぴったりです。また、築100年以上の古民家を改装したカフェも多く、石舞台古墳やキトラ古墳を巡ったあとに、昔ながらの雰囲気の中でくつろげるのが魅力です。コーヒーや和スイーツを楽しみながら、古墳の話で盛り上がるのも楽しい時間になるでしょう。
桜井市・天理市方面では、地元の茶畑を生かした「大和茶スイーツ」や、「柿の葉寿司」などの名物が味わえます。柳本町周辺には地元食材を使ったランチを提供するカフェや食堂もあり、黒塚古墳の見学後に立ち寄るには絶好のロケーションです。
また、馬見古墳群のある広陵町・香芝市エリアでは、公園内や近隣におしゃれなベーカリーカフェやジェラート店があります。花と古墳の散策後に、季節のフルーツを使ったパフェや地元野菜のランチを楽しめるスポットは、女性グループにも人気です。
古墳巡りは体力を使う活動だからこそ、地元の味でエネルギーを補給するのも旅の醍醐味です。事前にGoogleマップや食べログなどで「古墳名+カフェ/ランチ」と検索しておけば、移動ルートも無駄なく組めて快適です。観光と食の両方を楽しめるのが、奈良古墳巡りの大きな魅力のひとつです。
古墳関連のお土産・書籍・体験を探そう
古墳巡りの思い出を形に残すなら、関連グッズや書籍のお土産がおすすめです。奈良県では、古墳をモチーフにしたユニークなお土産が多数販売されており、歴史好きだけでなく、かわいいもの好きな人にも人気です。
代表的なお土産のひとつが、「古墳クッション」。前方後円墳の形をしたふわふわのクッションは、見た目のインパクトも抜群で、SNS映えもばっちり。奈良市や明日香村の観光案内所、オンラインショップなどで購入できます。
また、ポストカードやクリアファイル、マスキングテープといった文具類も充実しています。キトラ古墳の「四神」をモチーフにしたグッズは特に人気が高く、展示館の売店では限定アイテムも並びます。旅の記録に使える御朱印帳型ノートや、古墳柄の手ぬぐいもおすすめです。
書籍では、奈良県の古墳を解説した図鑑やガイドブック、ヤマト王権に関する入門書などが販売されています。飛鳥資料館や奈良文化財研究所の書籍コーナーは、学術的ながらもわかりやすい内容の本が多く、読み物としても価値があります。
さらに、近年では「勾玉づくり体験」や「土器絵付け体験」など、古代文化を体験できるワークショップも人気です。飛鳥エリアや橿原市では、家族連れでも楽しめる体験施設が充実しており、旅行の思い出づくりに最適です。
見て終わりではなく、「手に取る」「持ち帰る」「飾る」「学ぶ」ことで、古墳巡りの体験がより豊かになります。旅先でのお気に入りの一品を見つけて、日常に“古代”を持ち帰ってみてはいかがでしょうか。
なぜ古墳巡りで“歴史を体感”できるのか
古墳巡りの最大の魅力は、ただ知識を得るだけではなく、古代の空気を実際に“感じる”ことができる点にあります。教科書や博物館では伝わりにくい“生きた歴史”が、現地に立つことで一気に実感に変わる——それが古墳巡りの醍醐味です。
まず、古墳はその場所にあること自体に意味があります。なぜその土地に築かれたのか、どんな景色を見ていたのか、どのような力を持つ人物が葬られたのか。そういったことを、実際に歩きながら考えることで、歴史は抽象的な情報から“物語”へと変わります。
例えば、箸墓古墳の前に立ったとき、「ここに卑弥呼が眠っているかもしれない」というロマンがよぎります。石舞台古墳の巨大な石室に入れば、かつて誰かがこの中に葬られたことを想像せずにはいられません。キトラ古墳の精緻な壁画を見れば、当時の人々が持っていた宇宙観に触れることができます。
こうした体験は、書籍や映像では得られない“身体を通した理解”を与えてくれます。風の音、土の匂い、木々の揺れ——それらすべてが、かつてそこに生きた人々の気配を感じさせてくれます。
古墳巡りは単なる観光ではなく、「今と過去をつなぐ旅」です。何千年も前に作られたものが、今もなおその姿をとどめていることの驚きと感動。その場所に自分が立っているというリアリティ。それこそが、古墳巡りの本質的な魅力です。
次回の古墳巡りに向けたチェックリスト
奈良の古墳巡りは、一度訪れると「もっと見たい!もっと知りたい!」という気持ちが自然と湧いてくる奥深い旅です。初めての古墳巡りを終えたら、次に向けて計画を立てるのも楽しみのひとつです。ここでは、次回の古墳巡りをもっと快適で充実させるためのチェックリストをご紹介します。
【1】訪問した古墳の記録を残そう
写真はもちろん、どの古墳を訪れたか、どんな感想を持ったかをノートやスマホにメモしておきましょう。後から振り返ると、感動がよみがえりますし、次回の計画にも役立ちます。専用の古墳手帳や御朱印帳風の記録帳を使うのもおすすめです。
【2】次に訪れたい古墳をピックアップ
今回訪れなかった古墳で、気になったものはありませんか?例:高松塚古墳(壁画公開時期限定)、天理市の天皇陵、藤ノ木古墳(斑鳩町)など。公式観光サイトや古墳地図を使って、次に行くエリアをざっくり決めておくとスムーズです。
【3】季節を選んで再訪計画を
春・秋はもちろん、冬の静けさや夏の緑も魅力的です。次はどの季節に行きたいか、花の見頃やイベント情報も調べてみましょう。馬見丘陵公園などでは、季節の花祭りやライトアップイベントも開催されています。
【4】移動手段と宿泊を再検討
1日で回れなかった場合は、次回はレンタカーや宿泊を組み合わせるのもおすすめです。とくに明日香村や山の辺の道周辺など、じっくり時間をかけて巡りたいスポットでは、1泊することで見落としを防げます。
【5】古墳巡りを続ける“仲間”を見つけよう
SNSで「#古墳旅」などのハッシュタグを検索すると、他の人の体験や情報が得られます。共通の趣味を持つ仲間を見つけると、さらに楽しく、継続的に古墳巡りを楽しむきっかけになります。
このように、旅の記録を整理し、次の計画を立てることで、古墳巡りは“単発”ではなく“趣味”へと進化していきます。ぜひチェックリストを活用し、自分だけの古墳旅スタイルを育てていきましょう。
まとめ
奈良県の古墳は、単なる「古いお墓」ではありません。それぞれが歴史の語り部であり、古代日本の人々の営みや信仰、政治の痕跡を静かに今に伝えています。箸墓古墳の神秘、石舞台古墳の迫力、キトラ古墳の繊細な美しさ——ひとつひとつに個性があり、訪れるたびに新たな発見と感動が待っています。
本記事で紹介したように、奈良の古墳巡りは初心者でも楽しめるスポットが多く、アクセスも良好。史跡だけでなく、花やカフェ、体験施設なども充実しており、誰でも気軽に歴史に触れることができる“やさしい旅”です。そして一度踏み込めば、その奥深さに引き込まれる“魅惑の旅”でもあります。
古墳を通じて、古代の人々が見た空、感じた風、そして祈りを、私たちも少しだけ感じることができます。それはきっと、現代を生きる私たちにとっても心の豊かさや癒やしを与えてくれるものです。
ぜひ一度、奈良の古墳を訪れてみてください。そこには、静かだけれど確かな歴史と、あなた自身の新たな発見が待っています。そしてきっと、奈良のことが今よりもっと好きになるはずです。